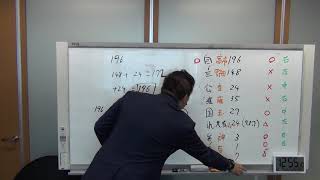自民党総裁選で高市早苗さんが勝利しました。
今後の政局について、立花孝志党首、倉山満さん、お二人の見解を紹介します。
立花孝志党首。
要約は以下の通り。
概要(一言)
高市新総裁=次期首相は“未確定”。鍵は公明党の去就と野党側の連携次第で、連立の再編如何では首班指名の数が逆転し得る、という情勢分析と、それを踏まえた立花氏自身の選挙戦略表明。
現在地の確認と誤解の是正
- 自民党総裁=自動的に首相ではない。これから国会の首班指名選挙で多数を取った側が首相になる。
- これまで(石破体制の時点)と違い、「自民+公明」で単独過半(233)に届かないため、連立の組み方次第で結果が動く。
議席配置
- 衆院定数465。自民196、公明24、立憲148(冒頭では147言及もあり)、維新35、国民27、れいわ9、共産8、有志の会7、参政3、保守1、無所属6〜7 などの数字を置いて議論。
連立シナリオと力学
- 自民中心(高市内閣想定)
- 伝統型の「自民+公明」だと合計220で過半数に届かず。追加パートナーが必要。
- (小泉新総裁だった場合の仮想)「自民+公明+維新」で255となり安定多数のシナリオが現実味、との回顧。
- 公明が離脱する場合
- 公明は「政権与党に入る」現実路線。高市氏の改憲・安保色にアレルギーが強く、立憲側と組む可能性が浮上。
- 立憲(148)+公明(24)+れいわ(9)+共産(8)+有志の会(7)=196で自民196と並ぶ“同数局面”も理論上あり。
- ここに維新(35)や国民(27)をどちらが抱き込むかで勝負が決まる。
- 例:立憲+維新で231、自民+国民で223となり、野党側が上回る計算例を提示。
- 人事カードでの交渉(例:野田佳彦を首班、山本太郎を財務相/維新・藤田氏を首班等)まで可能性として言及。過去の「自社さ連立(村山内閣)」の例を引き、意外な組み合わせも政治では起こり得ると指摘。
「公明の判断」が最大の焦点
- 公明が自民と再連立すれば高市首相の公算が高まる。
- 反対に、公明が自民と距離を取り野党側と協議に入れば、首班指名の数は一気に接戦〜逆転域へ。
- 高市氏が党人事を進める動き(萩生田氏起用など)や改憲・安保色は、公明・支持母体にとって受け容れ難い要素になり得る、との見立て。
各党の「解散」意欲と思惑
- 解散に前向き:自民(高市人気・期待感で勝機)、国民、参政(勢いを背景に議席拡大を狙う)。
- 解散に後ろ向き:立憲、公明、維新(現状維持/流動化回避)。
- 自民内には落選経験者を中心に「早期解散機運」が強まっているとの分析。
立花氏(N国/政治活動)の立場
- 高市政権誕生→年内〜年明け早期の解散総選挙の可能性が高まり、自身の再挑戦機会が来るため「高市を応援」表明。
- 参政党の伸長を“リスク”と見なし、「参政党から国民を守る党」で次期衆院選に出る構想にも言及(資金・情勢次第)。
- 政策的には、高市の積極財政には慎重だが「一度試してみたい」好奇心、対米(トランプ)・対中での強い交渉力に期待。ただし「パチンコはギャンブルではない」発言には違和感を示す。
スケジュール感
- 首班指名は当初「10/15(水)」開催予定とされたが、各党調整で後ろ倒しの可能性も示唆。公明の去就決定が情勢を一変させる“時限爆弾”。
まとめ(要点)
- 高市=自動的に首相ではない。議席算盤が割れ、決め手は「公明の選択」+「維新・国民の最終着地点」。
- 野党連携は“水と油”の壁があるが、人事取引・反高市の大義で“意外連立”が生まれる余地はある。
- 高市体制で解散なら与党有利の公算が高まり、立花氏は選挙再挑戦の好機と見て支援の立場。
- 直近最大の注視点:公明党の連立判断と、それに連動する各党の「首班指名」投票行動・人事カード交渉の行方。
別の観点から。倉山満さんの見解。公明党の連立離脱示唆を上手に利用せよ、という視点は大変興味深いです。
要約は以下の通り。
要約
- 公明党の「4条件」と連立示唆
公明党・斎藤代表は総裁選前から「高市(高一)氏とは組めない」趣旨の発言をしていたが、高一氏が総裁に。就任直後の党首会談で公明党は4つの注文を提示。公明党側は連立離脱も示唆し、一定のリスクを取ったと評価。- 高市側の基本姿勢(言語ニュアンスも含めた処し方)
高市氏は「了解、今後も仲良くしましょう」といった柔らかい京都風の言い回しで応じればよい、という語り手の提案(大阪弁や河内弁の“強さ”は避ける、というニュアンスの小ネタ)。- 4条件の中身:1「政治とカネ」
「政治と金の問題をしっかりせよ」という要求。
- 党務と政府を切り分け、内閣では問題のある人物を登用しない方針を徹底すれば応じやすい。
- ただし旧安倍派を全員外すことが現実的かは政権運営上の課題。
- 4条件の中身:2「靖国対応」
最も処理が容易。内閣法制局の従来解釈に沿う私的参拝で問題は回避可能との整理。
- 8月15日を避け、**春秋例大祭の時期に“私的に”**行くのが理屈として成立。
- 公明党は理屈を重視する政党であり、この線なら反対の根拠を作りにくい。
- ただし総理・外相・官房長官の参拝は外交面の波紋もあり政治力での調整が必要。
- 4条件の中身:3「外国人政策」
公明党が納得しないような極端策にはならない見通し。
- 語り手は、参政党が「レッテル貼り」を受けていることに触れつつ、差別的方針ではなく合理的ラインで収まるという見立て。
- 4条件の中身:4「大阪での選挙調整(維新との関係)」
最大の難所。
- 「維新と連立するなら大阪での公明の選挙に反対、選挙調整はしてほしい」という公明の要望。
- ここは総理(予定者)の権力を示しつつ“大人の交渉”で着地を図るべき局面。
- 全体戦略:高市側に“チャンスボール”
公明が連立離脱を示唆したことで、高市側は強気の交渉に出られる。
- 自民は最大会派・最大政党であり、総理予定者として正統性・主導権がある。
- 小泉純一郎や安倍晋三の時代も、公明を嫌いつつ自公連立は維持してきた事実を踏まえ、高市にも十分可能との評価。
- 落としどころのイメージ
「政治と金」「靖国」「外国人政策」の3点は比較的調整容易。最大のボトルネックは大阪での選挙調整(維新との関係)。
- 公明が先にリスクを取った以上、対価として首相権限を示して交渉するのが筋。
- 結果として**自公の“理屈が立つ妥協”**は十分あり得る、という見立て。
- 告知(倉山塾)
詳細や具体的な「公明党との付き合い方」はメルマガ本文(倉山塾)で解説、という案内。重要ポイントの抽出
- 公明の4条件は、①政治と金 ②靖国対応 ③外国人政策 ④大阪の選挙調整(維新)
- 難易度は④が最難関。他は法解釈・私的参拝・合理的政策設計で対応可能。
- 公明の“連立離脱示唆”は、高市側に交渉の主導権を与える「チャンス」。
- 歴代政権同様、**“理屈で立つ妥協”**に落ち着く蓋然性が高い。
補足的インサイト(示唆)
- 内閣人事:旧安倍派の処遇は「完全排除」か「段階的復帰」かで政権安定性が左右される。
- 靖国問題:国内“理屈”は通っても、対外関係は別軸。ここは外交当局の事前調整がカギ。
- 大阪問題:維新との距離感整理が国政・地方選の連動戦略に直結。ここだけは政治取引のコア。
上記、内閣法制局の従来解釈、という表現がありましたので、追加説明です。
結論だけ先に
- 参拝は「公的資格(公式)」か「私人(私的)」かで線引き。
- 私的参拝なら、①肩書を使わない、②費用は私費、③公務扱いにしない――等の外形を整えれば、政府として介入しない=憲法問題になりにくいという運用。(国立国会図書館)
- 背景には最高裁の「目的・効果基準」(公金で宗教を援助・助長しない)があるため、公金関与や“公的外形”を避けるのが肝。(cc.kyoto-su.ac.jp)
もう少し詳しく(実務の目安)
私的参拝と認められやすい外形(国会答弁・政府整理の積み上げ)
- 記帳や発信で肩書を使わない(「内閣総理大臣」等は書かない/言わない)
- 玉串料・献花代は私費(公金支出はしない)
- 公式日程・儀礼に組み込まない(“公務”に見せない)
- 随行・車両も可能な限り私的運用寄り
- 説明は一貫して「私人として」
…といった整理が、政府内資料や国会答弁にまとめられています。(国立国会図書館)なぜこの運用なの?
- 最高裁(1997.4.2「愛媛玉串料」)は、公金での玉串料奉納を「宗教への援助・助長」に当たるとして違憲判断(憲法20条3項・89条)。
→ だから政府は「公金は使わない(私費)」「公的外形を外す」を徹底してリスクを下げる、という考え方。(cc.kyoto-su.ac.jp)- 1980年代の経緯:政府は一時、「方式に十分配慮し、援助になる結果を避ければ公式参拝でも直ちに違憲ではない」とする整理を示したが、その後も制度化せず、各内閣が都度判断する姿勢を維持。結果として私的参拝へ収れんしてきたのが実務の実態です。(参議院)
日付(8/15)について
- 法律上の“合憲・違憲”は日付では決まらない(目的・効果が核心)。
- ただし8/15は政治・外交上の波及が大きいため、歴代政権は春秋例大祭期に“私的参拝”などでリスクを抑える運用が多かった、という政治判断の側面。(国立国会図書館)
参考になる一次情報
- 参議院・質問主意書/答弁:公式/私的の整理、費用・方式、車両等の扱いが具体的に記載。(参議院)
- 国立国会図書館資料:「閣僚の靖国神社参拝」懇談会資料(公式・私的の定義や過去答弁の整理)。(国立国会図書館)
- 最高裁判決要旨(目的・効果基準と公金関与の違憲判断の枠組み)。(cc.kyoto-su.ac.jp)
ひとことで運用指針
「私人の立場」+「私費」+「公的外形の排除」+「一貫説明」──これが“内閣法制局の従来解釈に沿う私的参拝”の最短ルートです。(国立国会図書館)
高市早苗さんによる靖国参拝、と言っても、公式参拝、私的参拝、という大きな違いの存在は理解しておきたいものです。