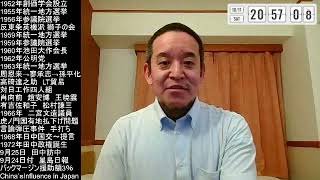公明党による自民党との連立離脱をきっかけに、公明党の勉強をしてみました。
1972年、田中角栄による日中国交正常化、これがきっかけで、日本の支援による中国の膨張、そして今や日本の脅威になっています。この1972年の件は、国策を誤ったといえます。
今回、福田博幸著、日本の赤い霧、の一部を読む動画を作りました。
要約は以下の通り。
動画要約
1) 冒頭の問題意識
- 2025年10月11日20:40時点の配信。前日、公明党が自民党連立を離脱したという前提で、「この機会に公明党を学ぶ」ことをテーマ化。
- 配信者(浜田聡/前参議院議員)は、Xでの反応を手掛かりに現実的な影響と今後の立ち回りを考える姿勢を示す。
2) Xの反応紹介(象徴的な二例)
- 住宅街で「公明+自民」両方貼っていた家が自民ポスターのみを素早く剥がしているという観察ポストを紹介(連立解消の地上戦への波及の早さを示唆)。
- 政策批判は可だが「公明党を立憲側へ追いやる必要はあるのか」といった冷静な意見を引用。少数与党となる場合は法案・予算成立で野党の協力が不可欠という現実論も紹介。
3) 『日本の赤い霧』(福田博幸)の第6章を読み解く(公明党・創価学会と対中工作)
- 焦点:周恩来が1956年頃から創価学会の政治的伸長に注目し、情報把握・対日工作に活用したとする叙述。
- 創価学会~公明党の台頭:1950年代後半から地方・参院選で組織票を積み上げ、60年代初頭に「公明政治連盟」→「公明党」へ。都議会・区議会で影響力を確立。
- 「対日工作4人組」:孫平化らを中心に、学会・公明のルートを用いて日本の政界人脈(作家・地方政治家等)に接触、影響力を拡大したとする主張。
- 田中角栄との接点:公明側が「田中疑惑追及」を手打ちで収束させた見返りに、新聞社への働きかけ等で利害が一致し、その後の日中国交正常化(1972年)に学会・公明ルートが関与したと描く。
- ODAと影響:国交正常化後の対中ODAが中国共産党・人民解放軍の力を強め、日本への軍事的圧力にもつながった、という著者の厳しい評価。バックマージン(リベート)を巡る噂話・記事引用も紹介(※著作の叙述として紹介)。
4) 歴史的論点と用語の取り扱い(動画内の説明)
- 「国交回復/正常化」という語の使い方を巡る倉山満氏の見解を引用し、1972年は「政府承認の変更」であり、言葉選び自体が北京のプロパガンダに沿うのではないかと問題提起。
- 田中角栄の「迷惑(ご迷惑)」発言エピソードに触れ、外交上の“弱み”として中国側に利用されたという見立てを紹介。
5) CSISレポートへの言及(概略)
- 2020年のCSIS報告「China’s Influence in Japan」を参照し、創価学会/公明党の平和主義的立場が対中融和的に作用しうる点や、憲法・安全保障への影響という観点で米側が注目・警戒している旨を紹介(概要の共有)。
6) 政策的提言(同書のまとめ部分の要旨)
- 台湾との関係の再評価・戦前戦後認識の整理、盧溝橋事件の性質の再検証、対中ODAの実績の可視化、民族主義的相互尊重に基づく健全な外交、21世紀的な平和的共存の枠組み確認――等の提案が列挙される(著者の主張の要約として紹介)。
7) 自身の所感・今後の方針
- 連立離脱を受けて公明党をただ「敵」に回す短絡は得策でない――国会運営の現実を踏まえた柔軟な戦術の必要性を強調。
- 自身の政治団体(日本自由党)や他勢力との連携・拡大を模索しつつ、中国共産党の影響力に負けないための“工夫”と機動力を重視する姿勢。
- 視聴者に高評価・登録・拡散を呼びかけつつ、『日本の赤い霧』(Kindle版含む)の参照を勧めて締めくくり。
まとめの一言
- 速報的事態(連立離脱)を受け、公明党/創価学会の歴史的形成と対中関係の文献(福田氏著)を素材に、日本の対中政策・与野党関係・世論戦の“基盤構造”を学び直す回。現実的な国会運営の要請と、対中影響力工作への警戒を両立させるべきだ、という問題意識が通底していました。
日本の赤い霧、ボリュームが大きい本なので、じっくりゆっくりと読んでいこうと思います。
日本の赤い霧(福田博幸著)Kindle 版を読んでいます。
極左労働組合の歴史
マスコミへの浸透
等、重要な内容満載です。
ーーーー
左翼の恐ろしさは、ほんの少数で組織の中枢に潜り込み、
組織全体をコントロールしうるほどの影響力を発揮
〜
今や第四権力といわれる「マスコミ」の内部にも浸透 https://t.co/314LN4jiDv— 浜田 聡 前参議院議員 NHKから国民を守る党💉💉💉 YouTubeやブログは毎日発信 (@satoshi_hamada) June 20, 2025
TBSをはじめとするテレビの偏向報道について
日本の赤い霧(福田博幸著)Kindle 版
この本の第7章が偏向報道の背景を説明しているように思います。
多くの方々が読むことを願っています。https://t.co/aE1qyEfH1Z#都議選2025 #自治労と自治労連から国民を守る党#民放労連 #新聞労連 https://t.co/CrmJ05jXQ7
— 浜田 聡 前参議院議員 NHKから国民を守る党💉💉💉 YouTubeやブログは毎日発信 (@satoshi_hamada) June 20, 2025