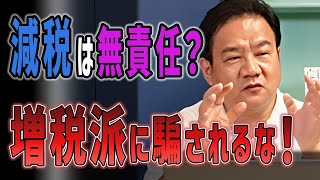今回は私も何度か出演している減税TVさんの動画を紹介します。
要約は以下の通り。
要約|〈第27回:減税!社会保険料引き下げの本当の話〉(2025/09/25)
概要(誰が・何を議論?)
■出演者
- 金子洋一(元参議院議員・OECDエコノミスト)
- 石川まさとし(医師/「社会保険料引き上げに反対する会」代表)
- 名嘉眞要(YouTuber・㈱Japan Pride代表/司会進行)
テーマは「減税は無責任か?」と、消費税・社会保障・社会保険料負担の関係。
金子氏がデータと制度設計の視点から、石川氏が医療・現場感覚から、名嘉眞氏が生活者目線の疑問を代弁しながら、“社会保障を口実にした増税論”の妥当性を検証。結論は「減税(とりわけ消費税・社会保険料の軽減)は、弱者保護としてむしろ責任ある政策」。
タイムスタンプ別の要点
0:00–1:03 OP/テーマ提示
- ネットで繰り返される「減税は無責任」論を正面から検証。
- 対象:①消費税は社会保障の安定財源論、②減税は高所得者優遇論、③制度変更に時間がかかる論。
1:03–5:52 「減税=無責任?」を精査
- 増税派の主張:消費税は医療・年金・介護の安定財源。減税には代替財源が必要、準備にも年単位で時間がかかる。
- 反論(主に金子氏):
- 消費税は一般財源で、厳密に社会保障だけに紐付けられていない(特別会計化されていないため使途の可視化が弱い)。
- 過去の増税(2014/2019)後も社会保障の体感的上積みは乏しい。
- 「社会保障を守るため」の名目が**“人質化”して増税の口実**になっている。
5:52–11:13 「社会保障=消費税で賄う」前提の限界
- 金子氏:令和7年度の消費税収は約25兆円。年金約70兆円、医療(保険関係除く)で約50兆円弱など、規模が全く釣り合わない。
- 石川氏:実務感覚としても消費税増収で社会保障が手厚くなった実感は薄い。一方で法人税は低下基調という構図。
- 名嘉眞氏:国会の歳出監視が弱く、メディアも軽減税率の利害で検証が鈍いのではという問題意識。
11:13–15:16 「高所得者ほど減税の恩恵が大きい」論を反証
- 金子氏(OECD流の家計負担率視点):
- 消費税は逆進的。絶対額では高所得者の減税額が大きく見えるが、負担率(家計への重さ)で見ると低所得層の改善幅が大きい。
- 例:年収200万円(全額消費)と年収1000万円(7割消費)で税率を引き下げると、低所得層の負担率改善(約2%ポイント)>高所得層(約1.4%ポイント)。
- 結論:「弱者保護のために消費税を下げられない」は矛盾。段階的に**8%→5%**などの引き下げが弱者を助ける。
15:16–16:02 給付設計(住民税非課税世帯中心)への疑問
- 石川氏:住民税非課税世帯の約4分の3は65歳以上。現役世代の負担(社会保険料・物価高)にリーチしにくい配分設計。
- 名嘉眞氏:結果としてばらまき的に見え、働く世代の生活防衛につながっていない。
16:02–END 本末転倒の是正=可処分所得を増やす政策へ
- 「社会保障を守るために減税不可」という発想で国民生活が圧迫されては本末転倒。
- 目的は国民生活の安定であり、手段(財源確保)が目的化してはならない。
- まとめ:消費税・社会保険料の負担軽減は“弱者保護として責任ある政策”。財政健全性との整合は歳出の重点化・無駄削減・成長政策とパッケージで次回以降に扱う。
役割別に見た示唆
- 金子洋一(制度・データ):一般財源の現実、特別会計でないこと、負担率での評価という設計論と計量視点を提供。
- 石川まさとし(医療現場):増税後も現場の実感が伴わないこと、現役世代の社会保険料負担の重さを強調。
- 名嘉眞要(生活者目線):国会・メディアの監視機能低下への違和感を代弁し、可処分所得を増やす政策の必要性を整理。
結論(番組の主張を一文で)
**「社会保障」を口実にした増税ではなく、**消費税と社会保険料の負担を軽くして可処分所得を増やすことこそ、生活弱者を守る“責任ある”政策である。
この動画のまとめ:消費税・社会保険料の負担軽減は“弱者保護として責任ある政策”。財政健全性との整合は歳出の重点化・無駄削減・成長政策とパッケージ。
ということで、上記のうち、無駄削減 のヒントになりうるのが次の動画。
要約は以下の通り。
要約|〈減税TV特別編:質問主意書の裏側を語る〉(2025/09/26)
概要(誰が・何を語ったか)
■出演者
- 村上ゆかり(コラムニスト/MC)
- 石川まさとし(医師・「社会保険料引き上げに反対する会」代表)
国会での質問主意書を作るまでの実務と、厚労省との事前レク(説明聴取)の実態を、具体的エピソードで解説。医療・介護・年金の制度運用が「使った分だけ膨らむ」構造になっており、政治の関与が薄いまま国民負担が自動的に増える問題を指摘。
タイムスタンプ別の要点
0:28〜2:04 出演者紹介/テーマ
- 特別編として、質問主意書作成の舞台裏と、厚労省への事前レクの中身を共有する回。
- 2025年通常国会頃から、浜田事務所の社会保障テーマに石川氏が助言。質問主意書40本規模を支援。
2:04〜11:33 作成フロー:事前レク依頼〜当日の進行
- **初回レク(1/30)**の依頼事項(抜粋)
- 国会採決不要で上がる社会保険料の範囲・根拠(「代表なくして課税なし」に反しないか)
- 終末期医療:事前指示書の法的拘束力の検討状況
- 医療・介護の費用対効果:保険給付から外す検討プロセス・実績(例:不妊治療年齢制限)
- 検査キット規制:インフル検査キットの薬局販売不可の理由(規制緩和観点)
- 年金:財政検証の前提や問題点(出生率・金利想定、外国人要因)、厚年金→基礎年金流用の根拠
- 厚労省側は複数局横断(保険局・老健局・年金局・子ども家庭庁 等)。当初1回で終える想定が大幅超過、レクは少なくとも11回に。
- 所感:局横断テーマは省内調整に時間。説明は各課が分担、全体像が分かりにくい。
11:33〜13:53 厚労省職員の社会保障認識(医療・介護中心)
- 医薬品:薬事承認(有効性)→原則6か月以内に保険収載という運用で、費用対効果評価が十分機能していない実態。
- 介護:費用対効果の枠組みが曖昧。介護/介護予防の定義自体が不明確との回答も。サービス価格は出来高積み上げで、やるほど給付が増える構造。
- 負担設計:介護保険は料率上限の仕組みがなく、総量拡大=税・保険料の負担が自動増。
- 官僚の説明姿勢:
- 「国が上げているのではなく、利用が増えるから上がる」と責任回避的ロジック。
- しかし価格・給付範囲は政策側が決めるため、設計責任は不可避。
13:53〜15:26 関心喚起と自己負担見直し
- “使い放題に近い”状態が需要を押し上げ、現役世代の保険料を継続的に押し上げる。
- 自己負担割合の見直しで、利用者に選択と抑制のインセンティブを持たせるべき。
- 使う人と払う人が非対称(世代間)で、費用の見えにくさが政治的・社会的な鈍感さを生む。
15:26〜END まとめ
- 質問主意書は、こうした不透明な制度運用の可視化と政府答弁の公式化に有効。
- 今回は医療・介護を中心に1回分を紹介。反響があれば年金等の続編も検討。
- 視聴者には、国会を経ずに負担が増える仕組みを知ってほしい、という問題提起で締め。
重要ポイント(番組の示唆)
- 社会保障費は“自動増殖”設計:出来高・包括の組み合わせや保険収載慣行により、政治の意思決定を介さず膨張しやすい。
- 費用対効果と定義の曖昧さ:医療・介護ともに費用対効果評価の徹底・定義の明確化が急務。
- 負担と給付の非対称性:世代間の**“使う/払う”のズレ**が、制度全体の持続性を損なう。
- 政策手段:①自己負担(定率・定額)の精緻化、②保険収載の厳格審査(費用対効果)、③給付範囲の再設計、④質問主意書での論点形成と答弁拘束。
一言まとめ
**「国会を通さずに負担が増える」社会保障の設計を可視化し、**費用対効果・自己負担・給付範囲を再設計するために、質問主意書を戦略的に使うべきだ——という実務的な問題提起の回。
皆様、YouTubeの減税TVへのチャンネル登録をお願いします。