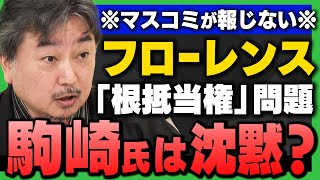今回もインターネット番組のニッポンジャーナルの番組内容を紹介します。
その前に、番組内容と関連する事例の紹介。
要注目案件
ーーー
渋谷区は、代々木四丁目の293平方メートル土地(資産価値約10億円相当)を、NPO法人フローレンスに対し月額5万8607円で貸与している。
病児保育事業を目的とするものの、賃料が著しく低廉である。
区民の公有財産が特定団体に不当利益を供与する疑念が生じる中、議員らは黙認? https://t.co/ZNwLI1z3wk
— 浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube&ブログ毎日更新 (@satoshi_hamada) October 28, 2025
SAKISIRU新田哲史さんの動画に注目!
渋谷区の補助金と区有地で建てたフローレンス施設に、本来禁止されている根抵当権が設定されていたという重大な制度・税金問題を、区議が動き始めている一方で大手メディアがほとんど報じていない構図を批判した内容です。
以下、要約:
—
■ 問題の概要
— 浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube&ブログ毎日更新 (@satoshi_hamada) November 15, 2025
SAKISIRU新田哲史さんの動画に注目!
渋谷区の補助金と区有地で建てたフローレンス施設に、本来禁止されている根抵当権が設定されていたという重大な制度・税金問題を、区議が動き始めている一方で大手メディアがほとんど報じていない構図を批判した内容です。
以下、要約:
—
■ 問題の概要
* 認定NPO法人フローレンス(創業者:駒崎弘樹氏)が、2017年に渋谷区内で「親子基地渋谷」という複合施設を開設。
* この施設には
* 渋谷区の補助金:約9700万円
* 日本財団の助成金:約3400万円
→ 合計約1億3100万円の公的資金が投入されている。
* 土地は渋谷区有地を割安で借りており、「税金+区有地」で成り立つ公的色の非常に強い施設。
* 当初、渋谷区には「抵当権を設定する」と申請していたが、実際には「根抵当権」が設定されていたことが登記から判明し、これが補助金適正化法に反する疑いとして問題化している。
—
■ 抵当権と根抵当権の違い(動画でのかみ砕き説明)
* 抵当権
* 住宅ローンなどで典型的に使われる。
* ある特定の債権(例:○○万円の住宅ローン)を担保するために不動産に付ける。
* ローンを完済すれば抵当権は原則として抹消される、一回完結型。
* 根抵当権
* 事業資金の借入など、継続的に「借りては返し、また借りる」タイプの取引で使われる。
* 一度設定すると、当事者の合意が続く限り、「限度額の範囲内で何度でも借入ができる」構造。
* 担保としての関係が中長期にわたり、内容も複雑。抹消にあたっては銀行側の同意が必要になるなど、簡単には外せない。
* 民間の社長が自宅に根抵当権を設定して事業資金を借りる……といったケースならあり得るが、
* 補助金で建てた公共性の高い施設
* しかも区有地上の建物
に根抵当権を設定するのは「絶対にやってはいけない」類の行為だと説明。
—
■ 法律上の問題点
* 補助金適正化法22条では、補助金で取得・整備した資産について
* 譲渡
* 担保設定
などを原則として禁止。
* 例外的に抵当権を認める場合でも、「対象となる債権が明確」「行政の事前承認がある」などの条件付き。
* 今回は、
* 渋谷区には「抵当権」の申請が出ていた
* しかし現実には「根抵当権」が設定されていた
というズレがあり、* 公的資金で建てた施設を使って、繰り返し融資を受けられる状態にしていた
→ 補助金適正化法の趣旨に明確に反する行為だと指摘。
—
■ フローレンス側の対応
* 渋谷区からの指摘を受け、フローレンスは「補助金交付要綱等に対するご指摘と対応について」という文書を公表。
* 内容は
* 交付要綱に適合しない点(=根抵当権設定)があったことは認める
* 「ご指摘を重く受け止め、反省しています」と表明
* しかし現時点では
* なぜ根抵当権を設定したのか
* 誰がどういう判断でそうしたのか
* どう是正するのか
など、原因究明や具体的な対応策は示されていない。
* 今後、税金の使途や公的資金の扱いとして、より詳細な説明が求められる段階だと述べている。
—
■ 問題を掘り起こした人物と制度の「マニアックさ」
* 初期の追及者は、大郷大輔氏(保育事業を行う事業者)。
* 以前からX上で駒崎氏やフローレンスの在り方に疑問を呈し、議論を重ねてきた人物。
* 登記情報等を調べる中で、この根抵当権設定を発見したとされる。
* 大郷氏によると、
* 補助金適正化法22条や、補助金物件への担保設定制限をきちんと理解している銀行員は少なく、
* 市中銀行は「使い回しできるからとりあえず根抵当権」のようなノリで提案してしまうケースもあるらしい。
* ただし、どれほど制度がマニアックでも、
* 公益事業者(認定NPO)が
* 補助金で建てた建物に
* 根抵当権を設定することは「絶対NG」
であり、渋谷区も含め「チェック体制が甘かった」と批判している。
—
■ 渋谷区議会・地方議員の動き
* 渋谷区議会では、すでに一部会派の議員(菅田氏、鈴木憲法氏ら)が問題視し、区に申し入れ・追及を開始。
* 今後、議会で正式に取り上げられ、区としての説明・対応が問われていく見込み。
—
■ オールドメディア(記者クラブメディア)への批判
* この問題は、SNS上では3週間ほど前から炎上気味になっているにもかかわらず、
* Googleニュースなどで見ても、報じているのはcokiの記事くらい。
* 朝日新聞・読売新聞等の大手紙のウェブ記事では、少なくとも目立つ形では取り上げられていない。
* その背景として、話者が挙げたポイント:
1. **NPOに対する「応援体質」**
* リベラル系メディアは長年NPOを好意的に取り上げ、駒崎氏も読売で連載を持つなど、メディアにとって「使いやすい人物」だった。
* そのため、不祥事が出てもチェックや批判が甘くなりがち。コラボ問題の時も似た構図が見られた。
2. **取材体制・人事の問題**
* 警視庁・裁判所・都庁などは「3大主力部署」で人も厚いが、区役所・市役所は「地方版扱い」でローテーション要員が多い。
* 記者の異動が激しく、数カ月〜半年で担当が変わることもあり、行政制度や財源構造に精通した記者が育ちにくい。
* 事件・スキャンダル取材には強くても、「補助金適正化法」「行政手続」「制度設計」など地味で複雑なテーマに強い人材が区役所担当に回らない。
3. **メディアのリソース不足**
* 近年、新聞社は人員が減り、どうしても「花形部署優先」になる。
* 区役所・市役所など基礎自治体の取材は後回しになり、結果としてこうした構造的な問題の追及が鈍くなる。
* 話者は、こうした構造問題を指摘しつつ、「地方議員がすでに動いている以上、記者クラブ系メディアもしっかり取材すべきだ」と強く求めている。
—
■ 動画の締めくくり
* 渋谷区とフローレンスの根抵当権問題は、
* 一見マニアックだが、
* 実際には「補助金」「区有地」「公的資金の使い方」「NPOと行政の関係」などが絡み合った重大なスキャンダルの芽だと位置づけ。
* 兵庫県での問題(斎藤知事をめぐる一連の騒動)や都政で佐藤さおり都議が追及している案件とも「構図が似ている」とし、
* 地方自治体の不透明なカネの動き
* それを十分に検証しないオールドメディア
という共通課題があると指摘。
* 今後も自身は兵庫の件などと並行しつつ、フローレンス問題も機会があれば追いかけていきたいと述べ、
* 視聴者にはチャンネル登録・高評価、さらなる関心を呼びかけて動画を締めている。
というわけで、本題、11月18日(火)の番組。
まずは切り抜き動画から。フローレンス問題について。
要約は以下の通り。
ざっくり言うと、「フローレンス+駒崎弘樹氏による補助金・寄付スキーム」と「渋谷区公有地+根抵当権」の“公金チューチュー構造”を、内藤さん・伊藤さんがかなり厳しく解説している回です。
1.フローレンスと駒崎氏の「お金の集め方」の問題点
- フローレンスは、過去に「ベビーライフ事件」とも関係が疑われてきた団体とされる。
- ベビーライフという団体が国際養子縁組事業を停止したが、海外に出された日本人の子ども174人のその後が不明で、「人身売買の隠れみのではないか」という疑惑があった。
- フローレンスは直接ではないが、その周辺に関与していた可能性があると指摘。
- 駒崎氏は、フローレンスの事業のためと称してクラウドファンディングを行い、
- それを渋谷区のふるさと納税の対象にして資金を集めた。
- 集まりが悪いと、自分で大口寄付を入れて「ふるさと納税」として税控除を受けつつ、その資金をフローレンスに還流させた疑いがある。
- 企業向けのスキームも指摘される:
- 企業が売れ残り品を認定NPOに寄付すると、「定価」で損金算入できるので法人税が減る。
- NPO側はほぼタダ同然で仕入れたものを「貧困家庭の食支援」などの名目で使いながら、別途寄付金も集める。
- ところが集まった金が、本来の事業ではなく、代表や幹部の高額報酬やぜいたくな生活費に使われているのではないか、という疑念。
- 駒崎氏は問題化直前まで、X(旧Twitter)に「高額サウナで仲間と遊ぶ」動画を上げており、「ほとんどラブホじゃん」と笑っている様子が見られた。
→ 「お金がなくて困っている人」では全くなく、むしろ“叩けばほこりが出る”タイプだと二人は見ている。
2.渋谷区公有地と補助金+根抵当権の構図
- 問題の土地は渋谷区の公有地(代々木あたり)。
- ここをフローレンス側が月額5万8,000円・30年間で借りる契約。
- 周辺相場は月100万円以上と言われるエリアであり、明らかに破格の条件。
- その土地に、総額1億円の補助金を使って建物(障害児保育施設+病院機能の複合施設)を建てた。
- 建設期間中の地代は“タダ”。
- つまり「公有地 激安貸し+建設費は税金」という、ほぼフル補助の優遇案件。
- さらにこの建物に根抵当権を設定していたことが判明。
- 普通の「抵当権」は特定の債権(例:工事代金の借入)を担保にするもの。
- 一方「根抵当権」は、設定上限の範囲で**何度でも借りて返してを繰り返せる“枠”**で、
- 不動産の価値の範囲内で、
- かつ、不動産とは関係のない事業資金などにも流用できてしまう。
- 補助金事業での担保設定自体は、法律上まったく禁止されてはいないが、
- 「補助金目的の施設に根抵当権を付け、限度額いっぱいまで別用途の借入に使える状態」は、補助金の趣旨に反する可能性が高い。
- フローレンス側は、当初「特定の工事代金などに対する抵当権の予定」と説明していたはずが、実際には根抵当権だったため、渋谷区を“騙していた”構図だと二人は批判。
- なお、銀行側も本来なら渋谷区に「この物件に根抵当権を設定していいか」と照会するはずで、
- 照会していないなら金融機関のガバナンス崩壊。
- 照会していたなら、渋谷区は承知のうえで認めていたことになり、行政側の責任が極めて重い。
3.事業内容の“すり替え”と公金チューチュー構造
- 当初の約束では、
- 障害児保育と医療(病院)を「だいたい半々ぐらい」で運営する前提。
- NPOは本来「採算は厳しいが社会的に必要な分野を担うからこそ補助金が出る」という立て付け。
- ところが実際には、
- 障害児保育は6年ほどで閉鎖。
- 代わりに儲かる病院部分をどんどん拡大。
- しかも、それも元手は渋谷区の補助金と優遇された公有地利用。
- フローレンスには15億円超とも言われる多額の内部留保・余剰金が溜まっており、
- 補助金も右肩上がりで膨らんでいると指摘。
- 二人はこれを典型的な**「公金チューチュー」**(税金吸い取りビジネス)の構図だと断じている。
4.政治・行政・メディアへの波及と“闇”の深さ
- もし単なる「税金にたかる悪質NPO」なら、まだよくある話で済む余地があるが、
- フローレンスや駒崎氏は、
- 共同親権問題
- 子ども家庭庁・男女共同参画など
- 児童・家族政策の分野で
政治家や官庁に強い影響力を持つ存在だとされる。
→ 単なる補助金問題ではなく、「政策決定プロセスに食い込んでいる団体」が公金チューチューしている構図がより深刻だと強調。- 問題はネット上で「根抵当権はさすがにアウトではないか」と指摘されたことで一気に広まり、
- 11月15日にテレビ朝日が地上波で報道。
- 「よくやった」と一度は評価したものの、その後、他の大手メディアも含めて続報がピタッと止まった。
→ ここにも“見えない力”の存在を疑わざるを得ない、と二人は口を揃える。- かつて連立与党に入っていたある政党がこの案件に関わっているのではという噂もあるが、
- 現時点ではエビデンスが弱いため、「そういう話も出ている程度」にとどめている。
5.他の真面目なNPOへの悪影響と制度全体の問題
- 世の中には、
- 小さな事務所を借りるのも一苦労しながら、
- 本当に採算の合わない福祉・子ども支援を必死にやっている「真面目なNPO」も多い。
- しかしフローレンスのような事例が放置されると、
- 「NPO=どうせ補助金ビジネス」と一括りにされ、
- 真面目な団体への信頼・寄付・補助が冷え込む危険がある。
- 制度はどんなものでも必ず悪用する人間が出てくる。
- だからこそ行政・金融機関のチェック機能が決定的に重要で、
- 渋谷区の担当職員が、
- 単なる“おバカ”で見逃したのか、
- それとも“何らかの不透明な便宜・癒着”があったのか、
どちらにせよ重大な問題だと追及。
6.求められる説明責任と今後の政治的争点
- 駒崎氏について:
- SNSを閉じて雲隠れし、「謝罪して幕引き」では済ませてはいけない。
- どこにどういう責任があるのか、資金の流れも含めて徹底的な説明と検証が必要。
- 渋谷区について:
- 区長レベルまでこの案件を知らないはずがなく、「知らなかった」で済む規模ではない。
- 次回の渋谷区長選挙の主要争点にすべき案件だと指摘。
- 公的補助のあり方をゼロベースで見直さないと、区民・国民の信頼は取り戻せない。
- 二人の結論:
- これは単なる一NPOの不祥事ではなく、
- 補助金行政、
- 公有地の貸し出し、
- 金融機関の審査、
- 政治との癒着、
まで絡んだ構造問題。- 「もっと大きく騒いで徹底的に洗い出すべき事案だ」として、視聴者にも関心を持ち続けるよう強く訴えている。
本編動画はこちら。
要約は以下の通り。
番組全体の流れに沿って、重要部分を中心に少し細かめに整理します。
1.番組導入とニュース一覧
- 冒頭は折島一平氏の司会。相撲の話題など雑談のあと、本日のゲストとして
- 伊藤俊幸:海上自衛隊 元海将(番組内では「低督」)
- 内藤陽介:郵便学者・国際情勢アナリスト
が紹介される。- そのうえで、番組で扱うニュース11本を提示:
- 在中国日本大使館の邦人向け安全注意喚起(高市発言のあおり)
- 高市総理(高市首相)の答弁を受けた外務省局長の北京派遣
- 朝日新聞の世論調査で高市内閣支持率69%
- 日韓共同訓練の見送り(竹島関連)
- ロシアが北朝鮮労働者を無人工場に動員
- インドネシアが海自中古潜水艦に関心
- 「陸自と海自のやり方全然違う」という現場記事
- 愛子さまラオスご訪問
- 共産党・釘宮氏の「赤旗はみかじめ料」発言
- 認定NPOフローレンスの謝罪・補助金問題
- いわゆる「回春行為」処罰検討のニュース
- YouTube視聴者は6番(インドネシア)、ニコニコ視聴者は10番(フローレンス)に注目が集まり、まずは⑩フローレンス問題から詳しく取り上げることに。
2.認定NPOフローレンスと根抵当権問題(内藤パート)
(1) 事案の概要
- 渋谷区・公的補助金を使って建てられた保育施設「親子基地渋谷」(2017年開設)が舞台。
- 補助金+格安区有地(相場100万円超のところ、月5万8千円で30年貸し)で保育・小児科併設施設を整備。
- 建物に対して金融機関から5,000万円を借りる際に「根抵当権」を設定。
- 補助金事業では担保としての「抵当権」は一定条件で認められうるが、「根抵当権」は趣旨に反する可能性が高い。
- 根抵当は「借りて返してを何度も」「用途も広範」に設定できるため、公的補助の目的外流用につながりやすい。
(2) 渋谷区と金融機関の責任
- フローレンス側は、当初「特定の工事代金等に対する抵当権」のように説明していたはずが、実際は根抵当権にしていた=区を“欺いていた”可能性。
- しかし金融機関も、区有地に根抵当をつけるにあたり、通常なら渋谷区に確認するはず。
- 確認していないなら金融機関のリスク管理がお粗末。
- 確認していて許可しているなら、渋谷区側も重大な責任。
- 渋谷区担当者は会見で「根抵当だと何度も借りられて問題だ」と説明しているが、伊藤氏・内藤氏は
「問題なのは、お前らが許しちゃったことだろう」と厳しく批判。(3) 事業実態と“公金チューチュー”疑惑
- 障害児保育園部分は採算が取れず、早々に閉鎖。代わりに儲かる病院部分を拡大。
- フローレンスには15億円以上の預金、10億円超の余剰金があると指摘されており、補助金の増加も続いている。
- 代表・駒崎氏は、高級サウナで遊ぶ動画なども投稿しており、「お金がないから苦しいNPO」というイメージとは乖離。
- 企業からの寄付を利用した節税スキーム疑惑、ふるさと納税の“自作自演”寄付疑惑など、過去から“叩けばいくらでもホコリが出る”と言われていた、と内藤氏。
- それにもかかわらず、子ども家庭庁や男女共同参画等の政策決定の周辺に深く入り込んでいることが、いっそう問題と指摘。
(4) 行政のチェック機能崩壊と政治的問題
- 本質は「フローレンスの問題+渋谷区(東京都)の監督責任の欠如」。
- コラボ問題と同様、NPOの不正だけでなく、自治体側のチェック・説明責任・情報公開の不備が大きい。
- 渋谷区長選の争点になるべきだし、公的補助全体のあり方の見直しが必要だと主張。
- 「税金足りない」と言いながら、こうしたNPOに巨額の公金が流れ、メディアも腰が引けて報じきれていない状況を批判。
- 渋谷区は自ら先頭に立って第三者委員会を設置するなり、駒崎氏を議会に呼んで説明をさせるべきだと強調。
3.インドネシアが海自中古潜水艦に関心(伊藤パート)
(1) インドネシアの位置づけと外交バランス
- インドネシアは将来日本のGDPを抜くとまで言われる有力国で、人口・経済両面で重要。
- 全方位外交を掲げ、日米とも中国ともバランスを取りつつ、どちらにも決定的には寄らない姿勢。
- 南シナ海の当事者だが、中国の直接的な軍事的圧力はフィリピンほどには受けておらず、そのぶん対中姿勢も“控えめ”。
(2) 防衛装備移転と中古艦艇活用
- かつて、アジア諸国から「日本の退役艦をくれ」とよく言われたが、武器輸出三原則等で実現不能だった時代が長かった。
- 今は「防衛装備移転」の枠組みで、一定条件下で輸出・供与が可能に。
- オーストラリアとの共同FFM建造や、フィリピン向け中古艦提供の例など。
- 中古潜水艦・護衛艦をインドネシアに渡すことができれば、防衛面での結びつきは同盟以上に強くなる可能性。
- 「武器を与えた国同士は、同じ“刀”を使う仲間になり、深い関係になる」という伊藤氏の持論。
(3) リスクと注意点
- 現大統領プラボウォはスハルト元大統領ファミリーの一員で、過去に汚職や人権侵害疑惑が多い人物。
- 武器輸出においては、公平な契約手続き・資金の流れの透明性を厳格に確保しないと、「怪しい勢力」に利用されかねない。
- とはいえ、日本の防衛予算拡大の国内ロジックとして、
- 「新しい装備を買う際に、古い装備を売ってコストを抑える」
という“小泉流の分かりやすい説明”は有効かもしれない、と内藤氏。
4.愛子さまラオスご訪問とラオス・日本関係(内藤パート)
(1) ご訪問の概要
- 愛子内親王がラオスを公式訪問(初の外国公式訪問)。
- 日ラオス国交樹立70周年の節目の年にあたり、
- 国家主席・副主席への表敬
- 不発弾問題啓発施設
- 日本語教育実施の中高一貫校
- 小児病院 などを視察予定。
- 番組では、これを日本の「ソフトパワー」「皇室外交」の重要な一環として評価。
(2) ラオスという国の歴史・豆知識
- 漢字の「ラオ」は、キセルの「ラオ」(竹の部分)にも使われる。
もともとラオス産の竹がキセルに使われていた、という説を紹介。- 歴史的にはタイの属国的立場から、フランス領インドシナへの編入、日本軍の「明号作戦」による一時的独立承認などを経て、戦後に主権を確立。
- 日本とラオスは1955年に国交樹立、その後、日本は水資源・インフラ整備などのODAでラオスを支援してきた。
- 特に、日本の円借款で建設された「第2タイ・ラオス友好橋」は、ラオス側にとって日本への感謝の象徴になっている。
- 切手デザインの話(桜とプルメリア、国旗モチーフなど)を交えつつ、日ラオス友好の歴史を紹介。
(3) 皇室外交の意味
- 東南アジアは「親中」「中立」「親日」など立ち位置が様々で、ラオスやカンボジアは中国寄りの色が濃い国とされる。
- こうした国々との関係維持・強化には、政治外交だけでなく皇室外交が非常に有効と伊藤氏。
- 愛子さまのご訪問は、日本の最強クラスのソフトパワー発揮の機会として評価される。
5.メイン企画:小泉進次郎・防衛大臣を徹底評価
(1) 以前の総裁選時の評価(おさらい)
- 9月末の番組で、小泉を「次期総裁有力候補」として扱った際の評価を再掲。
- 飯田泰之:見栄え・“顔”としては高評価、政策実現は「何もしなくても実現する政策」を掲げているので★3、総理適性は★1。
- 井上和彦:政策実現★1、党内人気★2、総理適性はなんと「マイナス1」。
- 批判点:
- 討論で守り一辺倒、自分の言葉で語っていない。
- コメント欄封鎖など、双方向性のなさ。
- “長老の操り人形”感。
- ただし「見栄え」「ファーストレディが滝川クリステル」という選挙向き要素は、プラス材料として認められていた。
(2) 伊藤・内藤が見る小泉像
- 内藤:
- 「林芳正より数万倍マシ」と再三強調。
- 小泉は政策的には“空っぽ”で能力も高くないが、その分ブレーン次第で良い方向に“振り付け”できる。
- 自分は頭がいいと勘違いして暴走するタイプ(林)の方が危険、と対比。
- 伊藤:
- 高市政権発足前後の頃はネット世論で「こいつはダメだ」と総叩き状態だった時期もあり、当時の低評価には理解も示す。
- ただし、横須賀選出であり、現場として自衛隊との接点は昔からあったのも事実、と指摘。
(3) 「覚醒」評価の背景:存立危機事態の国会答弁など
- 参院予算委員会での小泉答弁を、国民民主の新馬幹事長が「覚醒した感がある」と評価した記事を紹介。
- 特に、「台湾有事は存立危機事態となり得るか」などの質問に対し、
- 「基準を決めろと言う人もいれば、余計なことを言うなという人もいる。どちらを求められているのか私もよく分からない」
と、率直に“両方から板挟み”になっていることを吐露した点を、伊藤は「ある意味で本質を突いた」と評価。- これは官僚の書いたペーパーではなく、小泉自身の言葉だろうと推測。
- 伊藤・内藤の見立て:
- 小泉は「素直」「勘が良い」タイプで、やばいと思ったら引き返すことができる。
- 役人型の“優秀さ”(一度決めた方針を絶対変えない)とは真逆で、トップとしては「やめる決断」ができる人の方が良い。
(4) 「専門性不足」批判への反論とシビリアンコントロール論
- ネット上には「防衛の専門性がない」「具体策が見えない」という批判も多いが、2人はこれを一刀両断。
- 内藤:
- 大臣に専門性や実務経験そのものを求めるのは間違い。
- 基本方針を決めるのが政治家・大臣で、具体策や実務は官僚・制服組が担うのが本来。
- 専門性を持った“官僚型”がトップに立つと、方針転換(損切り)ができず危険。
- 伊藤:
- 「シビリアンコントロール」は防衛だけではなく、あらゆる省庁に必要な原則。
- 大臣に必要なのは、常識的判断と「おかしいものはやめる」と言える度胸。
- それができなかった歴史的失敗例として、戦前の対米戦開戦やコロナ政策等を引き合いに出し、「日本は“やめる”決断が常に遅い」と批判。
(5) 悪い大臣の例:あたご事件と石破防衛相
- 伊藤が「絶対やってはいけない大臣行動」の典型例として、イージス艦「あたご」と漁船の衝突事故を回想。
- 当初から「自衛隊が悪い」と決めつけたような言動。
- 片方(自衛隊側)の話だけ聞いて、すぐに“自衛隊が悪い前提”で遺族に謝罪に行き、まだ原因究明もしていない段階で印象を固定。
- 結果的に裁判で自衛隊側は無罪となったが、政治判断・メディア対応は完全に失敗だった、と厳しく評価。
- 一方、翌年別の衝突事故が起きた際、小寺防衛大臣は「片方の当事者である以上、正式発表までコメントは控える」と統一方針を出し、マスコミも冷静報道となり大騒ぎにならずに済んだ、と対照例を紹介。
- 「専門家ぶって勝手に先走る大臣」ではなく、「口を慎むべき時に引き締められる大臣」が重要だと強調。
(6) 進次郎の防衛大臣としての“適性”
- 防衛大臣になると、トップシークレット級の軍事情報が大臣だけに上がってくる。
- 小泉も本当に初めてリアルな軍事情勢を見て、「ここまでヤバい状況なのか」と強い危機感を持ったはず、と伊藤。
- そのショックが、最近の国会答弁での真面目さ、自分の言葉で語ろうとする姿勢につながっているのではないかと推測。
- また、防衛省での「栄誉礼」を受けることで、“自分はこのポストを預かる責任者なのだ”という自覚が芽生えることも、心理的に大きいと解説。
6.最終評価:星取り表と結論
番組最後に、伊藤俊幸・内藤陽介の2人が、小泉防衛大臣を3項目で5段階評価。
伊藤俊幸(低督)
- 防衛大臣としての適任度:★★★★★
- 高市内閣への貢献度:★★★★★
- 将来への期待度:★★★★★
- 現時点での防衛大臣としては非常に適任。
- 現場感覚・危機認識を持ち、シナリオがあれば役者としてきちんとこなすタイプとして高評価。
内藤陽介
- 防衛大臣としての適任度:★★★★★
- 高市内閣への貢献度:★★★☆☆(様子見)
- 将来への期待度:★☆☆☆☆
- 現在の防衛大臣としてのハマり方は「文句なし」だが、
- 小泉は「環境次第で180度変わる爆弾」のような人。
- 今は当たっているが、周囲次第でどう転ぶか分からないという危うさも大きい。
- よって、将来“総理”になった場合などを考えると、期待というより「ギャンブル性が怖い」という意味で★1。
7.まとめ
- 番組は、
- 渋谷区×フローレンス問題を「公金チューチュー」と自治体の監督不備の象徴として厳しく批判。
- インドネシアへの中古潜水艦移転構想を、防衛装備移転と対中包囲・外交の文脈から評価。
- 愛子さまラオスご訪問を、日本の皇室外交・ソフトパワーの重要な実例として紹介。
- そのうえでメイン企画として、小泉進次郎防衛大臣を
- 「本人は空っぽだが、それゆえにブレーン次第で良くも悪くも化ける」
- 「今のポストとブレーン構成の中では、むしろ“当たり”の人事」
と位置づけ、現時点の防衛大臣としては高く評価しつつも、将来のトップとしては慎重姿勢を崩さない──というトーンで締めくくっています。
内容盛りだくさんでした。これらから生成AIに教訓を考えてもらいました。
ざっくり整理すると、今回の話から引き出せる「教訓」はだいたいこんな感じだと思います。
1.フローレンス/補助金・NPO問題
- 公的補助金+公有地を使った事業は、「何に・どう使われているか」のチェックを行政側が徹底しないと、公金チューチューの温床になる。
- 根抵当権のように「何度でも借りられる・用途も広い」仕組みを補助金事業に使わせるのは、そもそも制度趣旨と相性が悪い。
- 事業者だけでなく、「渋谷区は本当に知らなかったのか」「金融機関はどう確認したのか」という“周辺の責任追及”が不可欠。
- 監督権限を持つ自治体が、「騙された側」なら率先して第三者委員会や議会招致をやるべきで、そこで腰が引けている時点でアウト。
- NPOや社会事業は、本来は“儲からない必要事業”を補うための仕組みであり、代表者への高額報酬+豪華ライフスタイルが当たり前になっていたら赤信号。
- コラボ問題同様、「団体個別の不祥事」にとどめず、補助金スキーム全体の見直し・再設計までセットで議論しないと繰り返す。
2.インドネシア・中古潜水艦・防衛装備移転
- 東南アジア各国は「表向きは全方位外交」でも、装備移転・共同訓練を通じて実質的な距離感は変わる。武器・装備の移転は同盟以上の“絆”を生む。
- 日本が中古艦艇や装備を適切に売却(供与)できれば、防衛予算の圧力を減らしつつ、対中牽制・プレゼンス向上に使える。
- ただし、受け手側(例:プラボウォ政権)の汚職体質・権力構造には細心の注意が必要で、「カネの流れ」と「契約プロセス」の透明性を確保しないと巻き込まれる。
- 防衛装備移転三原則などの縛りは、「安全保障上・外交上の合理性」に基づいて見直すべきで、イデオロギー的に自縄自縛になると国益を損なう。
3.愛子さまラオス訪問と皇室外交
- 東南アジアのうち「親中」「親米・中立」などグラデーションがある中で、日本は皇室外交という強力なソフトパワー手段を持っている。
- ODA(橋・インフラ・井戸など)と皇室外交をセットで積み重ねることで、「中国マネー一辺倒」にはなっていない国との関係を深められる。
- 官僚外交だけでは届きにくい国にも、皇室の公式訪問は“日本に対する好印象の蓄積”として効いてくる。
4.小泉進次郎防衛相「人事」からの教訓
- 大臣に本来求められるのは「専門家レベルの実務知識」ではなく、
- 情報を素直に受け取る感度
- おかしいと思ったら止める勇気(損切りの決断)
- 国民感覚から外れた判断をしない常識
であって、細部は官僚・専門家が担うべき。- 「専門性が高いオタク型大臣」が暴走・フライング発言をすると、アタゴ事件の石破防衛相のように組織と世論を同時に壊すリスクがある。
- 防衛大臣は事故・不祥事が起きた時こそ「片方の話だけ聞いて断定しない」「正式な調査結果が出るまでコメントを控える」という姿勢が決定的に重要。
- 小泉氏のように「中身は空っぽだが、ブレーン次第でどうとでもなるタイプ」は、
- 良いスタッフ・環境に置けばプラスに化ける
- 悪いスタッフ・環境だと一気に国益を損なう
という意味で、常に“周囲の顔ぶれ”をチェックし続ける必要がある。- 防衛相としての最近の答弁(存立危機事態の基準など)から見えるのは、
- ペーパーを超えて「自分の言葉で分からないものは分からないと言う」素直さ
- 二律背反の要求(基準を決めろ/決めるな)をそのまま指摘できる率直さ
であり、これはシビリアンコントロール上むしろプラスの要素。- ただし「覚醒した」と持ち上げすぎると、本人も周囲も勘違いしやすいので、「今のポジションと環境にはうまくハマっている」という冷静な評価を維持すべき。
5.政治全般・メディア・AIの扱い
- 大臣や政権を評価する際、「専門性が足りない」「経験が浅い」とだけ叩くと、結局“官僚型エリート”か“オタク型大臣”しか生き残らず、損切りができない危険な政治家が増える。
- 国会質疑のレベルが低いと、民主党政権期のように「相手の専門性をなじるだけの質問」になり、建設的な議論もシビリアンコントロールも機能しなくなる。
- チャットGPTを含むAIの要約・分析は「平気で間違える」前提で使い、特に数字や権限関係(誰が何を決めるか)は人間側で必ず検証する必要がある。
フローレンス問題は、私が現職時には全国会議員で私が一番問題意識をもって取り組んでいた自負があります。
今、国会議員として活動できないのは歯がゆいですが、国会の外でもできることをやっていこうと思います。