今回はウェストファリア体制について。
ウェストファリア体制とは?
ウェストファリア体制とは、
1648年に締結された「ウェストファリア条約」(三十年戦争の講和条約)を起点とする、近代国際秩序の基本原則のことです。
背景
- 三十年戦争(1618~1648年)
主に神聖ローマ帝国内での宗教対立(カトリックとプロテスタント)と、領邦や周辺国の政治的利害が絡み合った大規模戦争。- 長期にわたる戦争でヨーロッパ全土が疲弊し、宗教戦争終結と領土再編のために講和会議が行われた。
条約の内容と原則
- 主権国家の相互承認
- 各国(領邦・君主)が国内の政治・宗教を自ら決定する権利を持つ。
- 他国はその内政に干渉しない。
- 領土保全の原則
- 戦争前の国境線を基本に調整、国境を固定化。
- 宗教的寛容
- カトリック・ルター派に加え、カルヴァン派も公式に容認。
- 国際法の萌芽
- 国家間関係を宗教や普遍的権威(教皇・皇帝)ではなく、条約・外交交渉で管理する枠組み。
歴史的意義
- 「近代主権国家システム」の出発点とされる。
- 宗教権威(ローマ教皇)や帝国的権威(神聖ローマ皇帝)の国際政治への影響が大幅に縮小。
- 各国が対等な主体として国際社会を構成するという考え方が定着。
救国シンクタンク(チャンネルくらら)の動画を紹介します。
要約は以下の通り。
この動画は、国際法の成り立ちや性質、そしてウェストファリア体制との関係を、日本人が誤解しやすい点を踏まえて解説しています。
要点は以下の通りです。
1. 国際法の本質
- 国内法(刑法・民法)と違い、国際法は「超国家的な警察や裁判所」が存在して強制するわけではなく、各国が条約や慣習に基づき守る「合意の体系」。
- 「正義・悪」といった道徳判断よりも、軍事的合理性や実務上の必要性から発展してきた面が大きい。
- 国際法はあくまで「みんなで守った方が得」という積み重ねによって成立している。
2. グロティウスの思想
- 戦争自体を否定するのではなく、「戦争を前提にして、その中でやってよいこと・悪いことを区別する」という発想。
- 例:女子供を原則殺してはいけない(ただし戦闘参加などの例外あり)など、原則と例外の組み合わせで規範を作る。
- 戦争で人を殺すこと自体は必ずしも犯罪ではない。「戦争犯罪」は特定の行為に限られる。
3. ウェストファリア体制との関係
- 誰かが一方的に「正義の戦争」を決めてはいけないという考え方が、ウェストファリア体制の根幹。
- 戦争の正当性判断は、各国が対等な主権国家として行うべきもので、勝者が敗者に押し付けると惨禍を招く。
- この体制はもともとヨーロッパ発祥で、キリスト教世界内の秩序だったが、約300年かけて世界に広がった。
4. 日本人の誤解と問題点
- 日本では「人を殺すのはすべて悪」という感覚が強く、戦争中の殺害と平時の殺人を同一視しがち。
- 国際法の「原則と例外」の考え方や、軍事合理性との関係を理解していないケースが多い。
- 官僚や政治家が法学部出身に偏っているため、政策や国際法理解が形式主義に陥る傾向がある。
5. 歴史的補足
- ウィルソン以降、勝者による「正義の押し付け」(例:東京裁判、ニュルンベルク裁判)が広がったが、これは本来のウェストファリア的発想から外れる。
- 日本は国際法を「欧州の文化的産物」として受け入れた歴史があり、その背景を理解せずに適用すると誤解を招く。
まとめると、この動画は
国際法は正義論ではなく、国家間の合意と軍事合理性に基づくルール体系であり、ウェストファリア体制はその前提として「対等な主権国家同士の相互承認」を保障するものだが、日本ではこれらの本質が十分理解されていない
という指摘をしていました。
別の動画も紹介します。
要約は以下の通り。
この動画は、三十年戦争や宗教対立を軸に、西洋史の宗教・政治・軍事文化の特異性をユーモラスかつ辛辣に語りながら、戦争・略奪・国際秩序の本質を説明しています。
主なポイントは以下の通りです。
1. 十字軍と「バルタン星人」比喩
- 十字軍は自らを正義と信じていたが、外部(特にアラブ側)から見れば略奪や暴虐を行う「蛮族」。
- 例えとして、自分をウルトラマンと思い込むバルタン星人になぞらえ、自己正当化の滑稽さを指摘。
- アメリカの自己認識(世界の守護者と思っているが実際は力で従わせている)にも重ねる。
2. 宗教対立の過激さ
- カトリック vs プロテスタントは単純な二分ではなく、ルター派・ツイングリ派・カルヴァン派など内部抗争も激しかった。
- 宗教カルト化の危険性を、現代日本の新興宗教やネットワークビジネスにも通じる話として説明。
- 異端審問や宗教戦争は、暴力だけでなく社会的排除や経済的制裁でも人を追い詰めた。
3. 略奪と徴税の違い
- 暴力と権力の差は正当性の有無。略奪は暴力だが、徴税は「正当性」が付与された暴力=権力。
- 三十年戦争期、徴税制度は略奪抑制の手段にもなったが、実態は過酷で資源収奪の性格が強かった。
4. 三十年戦争の被害規模
- ドイツの人口の約3分の2が失われ、ペストに匹敵する壊滅的打撃。
- 宗教戦争は単なる戦闘ではなく、殲滅戦・住民虐殺・資産徹底奪取を伴う極端な暴力だった。
- 日本にはこの規模の内戦経験がなく、感覚的に理解しづらい。
5. グロティウスの意義
- 宗教的敵対関係にあっても「相手は人間である」という論理を持ち込み、人間性の回復を説いた。
- 詭弁的ではあっても、結果として多くの命を救う契機となった。
- これが後のウェストファリア体制の基盤の一つになる。
6. 日本人への示唆
- 日本は宗教戦争の歴史が薄く、こうした西洋の暴力文化や国際法成立の背景を理解しにくい。
- しかし日常でも宗教的・思想的排他は存在し、歴史知識はその予防策になり得る。
- 「戦争はなくならないが、戦い方を制限するルールは作れる」という発想を学ぶべき。
要するにこの章では、
三十年戦争の宗教的狂熱と暴力性、その中で生まれた「敵も人間である」という発想の意義を、現代的な比喩や皮肉を交えて解説し、日本人が歴史から学ぶべき“戦争と人間性の両立”という課題を浮き彫りにしている
という内容でした。
別の動画も紹介します。
要約は以下の通り。
この動画は、中西ヨーロッパの宗教戦争や国際法成立の背景を、グロティウスの思想やウェストファリア体制に焦点を当てて解説しつつ、宗教的独善性の危険性と現代への教訓をユーモラスに語っています。
主なポイントは以下の通りです。
1. 書籍構成とテーマ
- 第1章:グロティウスという天才
国という概念や国際法が未成立の時代に「国際社会」という発想を生み出し、戦争にも「やっていいこと・悪いこと」を区別するルールを構築。- 第2章:三十年戦争の惨禍
宗教対立による殲滅戦と住民虐殺の実態。- 第3章以降:ウェストファリア体制の成立、日本帝国の影響、そしてウィルソンによる体制崩壊と残存要素までの流れ。
2. グロティウスの革新性
- 国家や国際法が存在しない状況から「国際社会」と「戦争の規範」を構想。
- 戦争はなくならないが、戦いの仕方に制限を設けるという発想。
- 当時の「異教徒・異端は人間ではない」という価値観を相手も人間だと説得する論理に転換。
3. 宗教的独善と危険性
- どの宗教が最も危険か → 自らを宗教だと認識せず、唯一絶対の正しさを自認する宗教。
- 歴史的事実や相反する価値観を共存させるウェストファリア的発想が欠如すると、異端審問や魔女狩り、密告社会のような排除と粛清が横行。
- カトリックとプロテスタントの相互不寛容は20世紀の日本人間にも見られる。
4. 歴史的具体例と現代への示唆
- 魔女狩りの荒唐無稽な「証拠」や裁判手続きは、スターリン体制や全体主義と構造的に類似。
- 宗教戦争の殺戮規模は現代の紛争をはるかに上回る。
- 十字軍や宗教戦争は当事者にとっては正義の闘いだが、外部から見れば侵略・虐殺。
- 現代の政治思想や運動にも、この「自分の正義以外を認めない構造」が残っている。
5. ウェストファリア体制の核心
- 相反する価値観を持つ国家や宗教でも、相互に存在を認めることが国際秩序の前提。
- 「間違っていると分かっていても、それを言う権利を持つ」ことが主権平等の基礎。
- この発想が弱まると、再び宗教戦争的な排他と暴力が復活する危険がある。
要するにこの動画は、
グロティウスが築いた「戦争にもルールを」という発想と、ウェストファリア体制の価値である多様性の承認を解説し、それが宗教的・思想的独善を防ぐ鍵であることを、歴史的事例と現代の教訓を交えて示した内容
になっています。
別の動画も紹介します。
要約は以下の通り。
この動画は、ウェストファリア体制を基点に、日本の国際政治上の立ち位置・歴史的役割・現代課題を論じた内容です。特に、大国間パワーポリティクス(力の政治)と、その中で日本がどう振る舞うべきかが中心テーマになっています。
主な要点は以下の通りです。
1. ウェストファリア体制と日本の役割
- ウェストファリア体制(主権国家相互承認による国際秩序)は、大日本帝国によって本格的にグローバル化した側面がある。
- しかし、20世紀に入って二度の世界大戦とウィルソン的「聖戦思想」によって体制が揺らぎ、国際社会は野蛮化した。
- 本来の国際法はパワーポリティクスの中で守られるべきものであり、理念先行の国際連盟・国連憲章型国際法は現実と乖離。
2. アメリカ大統領たちの性質と問題点
- ウィルソンやルーズベルトは、自らを「正義の執行者(ウルトラマン)」と信じ込みつつ、秩序を破壊する行動を取った。
- トランプは例外的にパワーポリティクスを理解するタイプで、扱いやすい存在だった。
- アメリカの戦争観は「戦争」と「平和」を完全に切り分けるヨーロッパとは異質で、聖戦的発想を帯びやすい。
3. 戦争と国際法の変質
- 本来、戦争は宣戦布告を伴い、主権国家同士の関係で成り立つが、国連体制以降は非国家主体(ゲリラ・テロ組織)や宣戦布告なしの紛争が増加。
- グロティウス型の古典的国際法を理解しないまま現代の国際法を運用すると、パワーポリティクスが機能しない。
- 日本の戦国時代の外交(戦う理由を整えた上で開戦する習慣)は、実はウェストファリア体制的で理性的。
4. 現代の地域情勢と日本の対応
- 中国・ロシア・北朝鮮など、ウェストファリア的価値観(「相手を人間として認める」)が通じない相手には、まず日本が強くなることが必要。
- 朝鮮半島の安定には、日本が伊藤博文時代のように主導的に交渉・圧力を行える総理大臣の存在が重要。
- 韓国批判や竹島問題への感情的反応よりも、李承晩ライン撤廃など現実的課題の解決を優先すべき。
5. 基本的教訓
- ウェストファリア体制の核心は「相手の思想や価値観は否定しても、その存在は認める」という点。
- この価値観が通じない相手を、感情ではなく構造理解と力のバランスで扱う必要がある。
- 日本の国際行動は、理念だけでなくパワーポリティクスの現実を踏まえて設計すべき。
要するにこの動画は、
日本は本来ウェストファリア的秩序の担い手であり、現代の国際政治においても「力のバランス」を理解した上で動くことが不可欠だ。相手の価値観を変えようとするよりも、力で均衡を作り出し、その中で共存を図るべきだ
というメッセージでした。
この動画で語られていた根本博の功績は重要と思いますのでピックアップします。
- 時期:1945年8月、終戦直前〜直後。
- 状況:ソ連が日ソ中立条約を破棄して満洲へ侵攻、日本軍将兵や民間人が多数ソ連軍に捕虜として拘束され、シベリア抑留が始まる。
- 根本博の立場:当時、満洲方面の日本陸軍部隊を指揮していた陸軍中将。
- 命令違反の決断:日本政府や上層部からの武装解除・ソ連軍への引き渡し命令に従わず、独自判断で部隊と民間人を退避させることを決意。
- 行動内容:
- 部下や周辺の民間人を編成・護衛しながら、ソ連軍の支配地域から南方の米軍管理地域へ移動。
- 途中でソ連軍との接触を避けるルートを選び、戦闘回避を徹底。
- 規模:将兵・民間人合わせて約4万人をソ連軍の手に渡さず移送。
- 結果:彼らはシベリア抑留や強制労働を免れ、多くの命が救われた。
- 評価:戦後長らく公には語られなかったが、関係者証言や戦史研究で「戦後最大級の救出行動」とされ、台湾支援と並ぶ根本博の代表的功績として再評価されている。
日本が目指すべきものとして、パワーポリティクス型の日本外交が挙げられると思います。
1. パワーポリティクス型外交とは
- 国際関係は力がすべてではないが、最終的な安全保障は力で担保されるという前提で動く外交スタイルです。
- 軍事力、経済力、同盟関係など「相手に影響を与える手段」を組み合わせ、交渉や抑止を行います。
- 理念や人道支援は大事ですが、それは「国益と安全が確保されている」という土台の上に乗るものです。
2. 日本に当てはめると
- 日本は戦後、憲法・経済構造・安全保障条約の影響で、軍事面では米国に依存してきました。
- しかしパワーポリティクス型外交では、
- 自国の防衛力強化(軍事力・サイバー防衛・経済安全保障)
- 多層的な同盟網(米国同盟+インド太平洋諸国との安全保障協力)
- 経済力・技術力による交渉力(資源確保・サプライチェーン強靭化)
を柱にします。- 要するに「米国頼み一辺倒」から、「自分でも立てる外交」へシフトするのがポイントです。
3. 実際の行動イメージ
- 抑止:相手が攻めてこようと思わないだけの力と同盟関係を持つ。
- 均衡:中国やロシアが力を伸ばしたら、他の国との協力でバランスを保つ。
- 交渉力強化:貿易・資源・技術分野でカードを持ち、譲歩を引き出す。
- 地域秩序の形成:インド太平洋の小国支援を通じ、日本が影響力を持つ「友好圏」を広げる。
4. メリットとリスク
- メリット:安全保障の自立度が高まり、他国に振り回されにくくなる。
- リスク:軍拡競争や外交摩擦の激化、経済コストの増大。
この考え方は、ウェストファリア体制の「相手の主権を認めつつ、自国の安全を力で担保する」という発想と非常に相性が良いです。
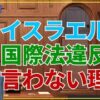

コメント
図書館で倉山満さんを検索すると沢山出てきます。
読んでみようと思います。
浜田さんの著書もリクエストしようかと思います。
浜田様
コメント失礼いたします。
私は動画配信者「Bappa Shota」氏の活動を日頃より拝見している者です。
同氏は、今年6月に中国・新疆ウイグル自治区に関連する動画を公開して以降、約1か月間にわたり更新が途絶えており、SNS上のファンや視聴者からは安否や安全性について深刻な懸念の声が多数上がっております。
心配している理由は以下の通りです。
1. 新疆ウイグル自治区は人権状況や取材活動に対して厳しい制限がある地域であり、過去にも外国人ジャーナリストや旅行者が拘束・尋問を受けた事例が存在します。
2. 中国では昨年「反スパイ法」が強化され、外国人による情報収集や記録行為が幅広く規制対象となっています。
3. Bappa Shota氏は現地で施設外観や周辺状況の撮影を行っており、これが現地当局の規制対象に該当する可能性があります。
本件は、表現の自由や日本国民の安全確保の観点からも、ご関心をお持ちいただきたい事案であると考えております。
つきましては、外務省や在外公館を通じた事実確認や、同様の事案再発防止に向けたご対応をご検討いただけますと幸いです。
参考リンク:
YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@bappashota
Instagram:https://www.instagram.com/bappa_shota/
お忙しい中恐縮ですが、ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
ウエストファリア体制の対極はウィルソン主義ではないでしょうかね。
野放図な多文化共生の背後にいるのは、中央や地方の中枢、学者、メディアにはウィルソン主義の信奉者(お花畑)がたくさんいて、知らず知らずのうちに国民の平穏と権利を奪っていく。そんな構図が目に浮かびます。
時折SNSでみかける、冷笑して衰退ポルノかましてクルド人を擁護する文脈で移民は仕方ないとか現状におもねる人の姿を見ると情けなくなってくる。そういう人は知性も感覚も弱っている人だと思います。すぐ音を上げる人、多くなったような。
日本という国の行く末そのものに対しては、諦めが悪く図太く生きたいものですね。先人がそうしてきたように。そのために学ぶことは大事ですね。