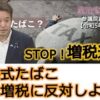今回は山本勝市氏について。
先日、私は新たな政治団体、日本自由党を立ち上げ宣言をしたわけですが、その件と大きく関係している重要な偉人です。
自由民主党になる前の「自由党」は山本勝市さんというハイエク研究の経済学者の自由経済の理論を支柱にした政党でした。しかし、保守合同で自由民主党になったとき、旧翼賛会系の民主党議員が流れ込んできてケインズ政党になってしまいました。その結果として、日本からは自由主義政党が無くなりました
— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) November 11, 2016
日本の戦後復興期に、社会主義、全体主義と戦った山本勝市博士について書かれた記事。山本勝市博士について書かれた記事は、そう多くはない。
渡瀬裕哉さんにチャンネルくららにご出演を頂くきっかけになったのは実はこのブログ。
〉自由党の党綱領には「計画」は存在せずhttps://t.co/vgfkbSxbOo— チャンネルくらら~日本に近代政党を❗ (@chanelcrara) April 27, 2020
山本勝市氏について、私は国会で取り上げたことがあります。
当該質問部分のみ抜粋。
〇山本勝市氏の福祉国家亡国論が今後の日本の社会保障制度の在り方を考えるうえで重要との観点から質問
・1.結論として社会保障は限界を設けること、が山本勝市氏の福祉国家亡国論にて述べられている。社会保障費が相当上昇しており、今後さらなる上昇が想定される中、山本勝市の福祉国家亡国論、社会保障は限界を設けるべき、という考え方は適切であると考える。日本政府による福祉国家亡国論、社会保障は限界を設けるべき、という考えに関する政府見解を伺う。→政務3役(官庁問わず、誰でも可)
参考リンク:【福祉国家亡国論より】社会保障の将来見通しへの疑問
https://note.com/localabo/n/n3bb1703f1a7b
(取り下げ)・2.1955年に自由党と日本民主党が合併して自由民主党となった。この時、以下の2つの系譜があり、対立していたとされる。
一.政府による民間への介入をできるだけ抑えるべきとする「自由主義経済」:山本勝市が綱領作成
二.政府が民間へどんどん介入していく「計画経済」:岸信介が主導
渡瀬裕也氏によると、毎年膨張し続ける政府予算と政府債務の有り様を見れば、旧自由党のエートスはほぼ失われた状況にある、とのことである。
http://yuyawatase.blog.jp/archives/06078.html
https://youtu.be/86tLWj1peBk
上記を踏まえて、山本勝市氏に関する評価を伺う→政務3役(官庁問わず、誰でも可)
会議録はこちら↓。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114601X01320230613¤t=1
要約は以下の通り。
浜田聡議員の「福祉国家亡国論」に関する質問と、それに対する政府側(畦元将吾 総務大臣政務官)の答弁は以下のとおりです。
📝 質問と答弁の整理
浜田聡議員の質問(要旨)
- 問題提起
- 国民負担率が5割近い現状を踏まえ、社会保障費の負担増大は国民生活を圧迫している。
- 日本自由党創設メンバーで経済学者の山本勝市氏の著作『福祉国家亡国論』を紹介。
- 山本氏は「社会保障には限界を設けるべき」と主張しており、過度な福祉国家は国民の自助精神を損なうと警告していた。
- 歴史的背景
- 1964年(昭和39年)の国会質疑で山本氏は「福祉国家の限界」を問うたが、当時の小林武治厚生大臣は「限界を論じるのはまだ先」と答弁していた。
- しかし現在は、その「限界」が既に到来、あるいは通り過ぎた状況だと指摘。
- 政府への問い
- 「社会保障は限界を設けるべき」という『福祉国家亡国論』の考え方について、日本政府としてどう考えるかを質問。
政府答弁(畦元将吾 総務大臣政務官)
- 社会保障制度の評価
- 日本の社会保障制度は「国民皆年金・皆保険」を根幹とし、自助・共助・公助を組み合わせてきた。
- これにより国民の長寿と生活安定を実現した「世界に冠たる制度」だと評価。
- 持続可能性への対応
- 将来にわたって持続させるため、給付と負担のバランスを不断に見直している。
- 具体例:後期高齢者医療・介護保険利用者・生活保護基準の見直しなど、歳出抑制策を実施。
- 今後の方針
- 「全世代型社会保障」を目指す。
- 能力に応じた負担と必要に応じた給付を行い、公平な支え合いを重視する。
浜田聡議員の再質問・コメント
- 政府答弁にあった「自助・共助・公助の順番」を評価。
- 山本勝市氏と『福祉国家亡国論』を国民にもっと知ってもらう必要性を強調。
- 問題点として、社会保険料は法改正なしで上昇できるため、増税よりもハードルが低く負担増につながっていると指摘。
- 提案:米国のように「給与税」として法改正のハードルを設けるべきだと主張。
- 今後も社会保険料を「給与税化」する提案を訴えていくと表明。
✅ まとめ
- 浜田聡議員は、山本勝市氏の『福祉国家亡国論』を引用し、社会保障には限界を設けるべきだと政府に問題提起。
- **政府(畦元政務官)**は、制度の成果を評価しつつ、負担と給付の見直しを重ねて持続性を確保していくと答弁。
- 浜田議員の主張は、社会保険料の無制限な増大を防ぐため、制度を税制化し、負担増に国会審議を必須とする仕組み導入を求めるものでした。
当該部分をまとめてくれた動画を紹介します。
最後に、私が政策立案でお世話になっている救国シンクタンクで、山本勝市氏に関するレポートのひとつを紹介します。
今回のメルマガで江崎研究員が取り上げている山本勝市博士は、戦前から戦中、戦後にかけて、一貫して自由主義経済に関する論文を発表されています。どのように皇室のお話とつながってくるのか、ぜひメルマガをご確認下さい。
当該レポートの冒頭部分を紹介します。※このレポート内容が素晴らしい、続きも読みたい、と思われる方は救国シンクタンクの会員登録をご検討ください。
◆◆救国シンクタンクメールマガジン 21/6/13号◆◆
評論家の江崎道朗です。
「なぜ民間シンクタンクが重要なのか」という観点から毎回、政治的課題について書いていこうと思います。
今回は、「自由主義と皇室」です。今回と次回は、二回にわけて戦前・戦中、そして戦後、自由主義経済を唱えた山本勝市博士を通じて、自由主義と皇室のことについて考えてみたいと思います。
リバタリアンを含む自由主義の理論的指導者のひとりがフリードリヒ・ハイエクです。このハイエクの先生にあたるのが、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス(1881年9月29日~1973年10月10日)です。ミーゼスはオーストリア=ハンガリー帝国出身の経済学者であり、現代自由主義思想に大きな影響を及ぼしました。
このミーゼスの議論を日本で最初に紹介した学者が、山本勝市博士だと言われています。
山本勝市博士は大正14年(1925)3月から昭和2年(1929)9月、文部省在外研究員として仏・独・ソに留学、そして昭和6年(1931)8月から昭和7年(1932)5月、ソ・独に私費留学をしています。
日本に帰国後、当時の日本で台頭しつつあった統制経済を批判する論文を次々に発表し、注目されるようになります。山本勝市論文選集『社会主義理論との戦い』(国文研叢書、昭和55年)の編者、三浦貞蔵(川崎製線〔株〕常務取締役)はこう述べています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MPQ2BC1/ref=cm_sw_r_tw_dp_E3A9AWFT26KGD29QH9CF《昭和十二年に支那事変が起り、わが政府は、統制経済の実施にふみきった。これに対して山本先生は一物の統制は、相次いで他物の統制を呼び、結局統制は全物資に波及せざるを得ず、市場メカニズムは衰滅して、やがて、政府の意図する「生産力拡充」、「国民生活安定」とは逆の結果を生ずるに至ることを、多くの文章で痛論されたのである。》
シナ事変の頃から日本では、革新官僚たちが「総力戦」の名のもと、統制経済に傾斜していくのです。戦前の日本のエリートたちが統制経済、社会主義に共鳴していた経緯は、拙著『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』で詳しく書いています。
文部省の直轄教育機関であった国民精神文化研究所の勅任所員であった山本博士は新体制運動、大政翼賛会などの動きのなかで統制経済が強化されていくこと憂い、それまでの批判論文をまとめて発刊したのですが、なんと絶版を勧告されてしまうのです。