川崎市長選挙2025、いよいよ投票日が近付いてきました。
事務事業評価で税金の使い道を正す党、宮部龍彦候補へのご投票をお願いします。
川崎市長選挙のスケジュールです。
・2025年10月12日(日)告示
・2025年10月26日(日)投開票
川崎市選挙管理委員会が5月12日、任期満了に伴う川崎市長選挙を、10月12日(日)告示、26日(日)投開票の日程で行うことを決定https://t.co/RDZ1hLo1nr— 新百合ヶ丘タイムズ (@shinyuritimes) May 25, 2025
私が市長になれば確実に実行されることを挙げておきます。
・ふれあい館の社会教育事業の中立化
―ここで何十年も在日コリアンと日本人の対立を煽る社会教育をしたことがヘイトの原因なので、断行します。
・本庁舎記者クラブの占有解消…— 宮部龍彦(みやべたつひこ) (@K_JINKEN) October 22, 2025
私が市長になれば確実に実行されることを挙げておきます。
・ふれあい館の社会教育事業の中立化
―ここで何十年も在日コリアンと日本人の対立を煽る社会教育をしたことがヘイトの原因なので、断行します。
・本庁舎記者クラブの占有解消
―あの立派な庁舎の部屋を記者クラブが契約書もなしにタダで占有してるのは不要な利益供与です。
・同和対策相談事業廃止
―川崎市に同和地区はないのだから、当然です
・民間団体の講演会への職員動員廃止
―神奈川県下の自治体が何十年もやらされていることですが、川崎市から率先して止めます。
・多文化共生社会推進指針から外国人地方参政権を削除
―市長権限でやれることなので即座にやります。
・SDGsパートナーまつり廃止
―今年が最後になることでしょう。
#宮部たつひこ #川崎市長選挙
・前参議院議員 浜田聡 代表の「事務事業評価で税金の使い道を正す党」公認候補
・投票日:令和7年10月26日(日)
・期日前投票:10月13日(月)~25日(土) pic.twitter.com/4HSALHYwkZ— 一般市民 (@PW_Walker_IV) October 13, 2025
https://www.kurashikiooya.com/2025/07/24/post-21231/
今回は、宮部龍彦候補の関連動画を3つ紹介します。
戸田市議会議員、河合祐介さんとの対談動画。
要約は以下の通り。
概要
- 川崎市長選(10/26投開票)を前に、宮部龍彦候補が出演。
- テーマは「しばき隊を含む左派系グループの妨害」「神奈川新聞の報道姿勢」「川崎市の人権・多文化施策のあり方」。
- 司会者は他自治体選挙の動向にも触れつつ、宮部氏の政策と選挙情勢をヒアリング。
宮部龍彦の略歴・活動軸
- 鳥取県出身。工業高→信州大→プログラマー。
- 2005年の「鳥取人権救済条例」騒動以降、人権・部落・同和利権を取材・発信。YouTubeで長年発信。
- 今回は「事務事業評価で税金の使い道を正す党」(浜田聡氏の政治団体)から市長選に立候補。
しばき隊・妨害の実態
- 川崎駅東口の街宣で大規模妨害が1回、ほか数回の小規模事例。
- 解放同盟系を含む左派系がプラカード等で抗議。司会者は「来られると逆に話題化する側面も」と言及。
神奈川新聞への批判
- 候補者一覧で宮部氏のみ顔写真が載らない等の扱いを問題視。
- 同紙・石橋記者による記事(ヤフーニュース転載含む)を「不公正」「レッテル貼り」と批判。
- 記者クラブの優遇(庁舎内無償利用等)にも問題提起し、「脱記者クラブ」(田中康夫方式)を示唆。
触れ合い館(桜本)・社会教育事業の論点
- 川崎市が実施してきた歴史・人権関連の社会教育が「対立を煽る」「中立性に欠ける」と指摘。
- 関東大震災・朝鮮人虐殺、戦時動員等の扱い方を批判し、「中立化(実質的な廃止・見直し)」を公約。
- 指定管理の福祉団体(青い丘等)について、子ども文化センター運営は概ね適正としつつ、社会教育部分のみを問題視。
同和・部落対策事業への異議
- 市の「同和対策・生活相談」の委託実態が不透明と主張。
- 団体の所在地・人脈が「川崎の被差別部落と無関係」との聞き取りや裁判資料の示唆を提示。
- 行政情報の黒塗り対応を批判し、情報公開と客観的検証(KPI重視)を強調。
外国人・ヘイト条例への見解
- 罰則付きヘイトスピーチ条例は「言論の自由」を阻害とし見直し・廃止志向。
- 行政が特定集団に忖度しているとの市民不信を懸念。川口市のクルド人問題を引き合いに、行政の公正性確保を最優先と主張。
主要公約・政策トーン
- 触れ合い館の社会教育「中立化」。
- 情報公開・表現の自由(市民・職員・議員の萎縮是正)。
- 記者クラブ特権の是正(撤去または有償化)。
- SDGsや理念型研修・コンサルの縮減(「理念先行に税金を使わない」)。
- 条例・規則の棚卸しと不要廃止。
- 男女共同参画の縮小(理念施策の見直し)。
- 「ブラック(部落)サービス」の廃止(利権化の是正)。
- パートナーシップ制度:性的少数者限定をやめ、同性・異性を含む事実婚・高齢者・障害者の生活支援連携枠へ拡張(防災・福祉の実利重視)。
- 事務事業評価の実効化(KPI導入、主観・アンケート偏重の是正、SDGs連動要件などの排除)。
選挙情勢・他候補評価
- 現職・福田紀彦は「自民~立憲までほぼ総与党」支援で強固。
- 野信あけ美(共産・立憲系無所属扱い)、山田えいじ(保守系・元自民)、関口みのる、やりたりょうた等が出馬。
- 宮部氏は「保守票の受け皿」を自認し、「まず共産候補越え」を当面の目標とする姿勢。
司会側との合意点・やり取り
- 「理念に金を使わない」予算技法に司会者が強く共感。
- 事務事業評価を施策レベルでKPI化し、客観指標で予算配分を見直す方向で一致。
今後
- 天候で一時休止したが、街宣は再開予定。
- 26日投開票の結果を注視。終了後もコラボや埼玉での街宣参加の可能性に言及。
以上です。
神奈川新聞の石橋学記者との議論の動画です。
要約は以下の通り。
概要
- テーマは、川崎市長選(10/26投開票)をめぐる神奈川新聞・石橋学記者への公開反論。
- 争点は「同和(部落)関連事業の実態」「市の情報公開の在り方」「記者の取材姿勢と検証責任」。
- 進行全体は、宮部氏(発信側)が“一次資料に基づく主張”を繰り返し、石橋記者(電話・対話想定の音声箇所)は「本人確認の不足」を突かれ続ける構図。
何が起きたか(流れ)
- 宮部氏が「川崎市の同和相談事業を担う関係者(土屋氏など)は“部落と無関係”だと自ら確認した」と主張。
- 石橋記者は「本人に確認したのか」「裁判資料や戸籍の確認は」と詰めるが、記者自身の一次確認が不十分と逆に突かれる。
- 「裁判資料で“空欄(ブランク)”になっている」点をめぐり、宮部氏は「出自を証明できなかった結果だ」と合理的推論を提示。記者は「推測だ」と反論するも、自身の確認提示はなし。
- 情報公開の非開示理由(悪用防止)を記者が擁護する一方、宮部氏は「そもそも“エセ同和”的な構造が前提の制度・要綱自体が不当」と制度論に拡張。
- 宮部氏は「本人(当事者)に行って直接聞け」「一次資料を自分の目で見よ」と繰り返し要求。記者側は具体的な新事実の提示なく応酬が空転。
- 終盤、宮部氏は「昨日と今日であなたの説明が変わっている=虚偽を流したのでは」と畳みかけ、神奈川新聞の信頼失墜を示唆して締める。
両者の主張・論点整理
- 宮部側
- 「当該“支部長”等は出自的に部落無関係」との聴取結果を提示(“浅草出身”等の具体情報に言及)。
- 裁判で“部落出身”認定が空欄になった点は「証明不能の帰結」と位置づけ。
- 川崎市の同和・人権関連事業は、実態や委託先の適格性が不透明で“利権化”の疑い。
- 情報非開示は「制度の歪み隠し」。開示すれば“エセ”が露呈するから隠している、という見立て。
- 記者クラブ的体質・レッテル報道を批判。「一次資料・本人確認」を行わない姿勢を“取材放棄”と断じる。
- 石橋記者側(対話内で表出した立場)
- 「本人に直接確認したのか」「戸籍や裁判書類は自分で見たのか」と“検証の厳密性”を要求。
- 非開示の理由は「差別の悪用防止」で妥当と主張。
- 宮部氏の推論(空欄=証明不能)には「推測」と反駁。
- ただし、自身の“現場確認・一次資料の提示”はこの場で具体化できず劣勢。
エビデンス位置づけ(番組内での扱い)
- 宮部氏は「一次資料のコピーを出している」「聴取録がある」と主張。
- 「裁判資料の空欄」「所在地が市外(横浜)」など、制度・人選の不整合を列挙。
- 記者側は“確認して聞いた”と受動的に言う場面はあるが、当該配信中に具体資料や本人取材の成果は提示できず。
論点の核心
- 本人確認の徹底:報道側の取材倫理(一次確認)と、疑義を呈する側の証拠提示の在り方。
- 制度の適否:川崎市の同和・人権関連事業―委託先の適格性、根拠資料、要綱設計の妥当性。
- 情報公開と差別防止:非開示の名目(悪用防止)と、市民監視(説明責任)とのバランス。
- 選挙報道の公平性:候補者扱いの格差、レッテル報道、記者クラブ特権の是非。
受け手への印象(番組の示す絵柄)
- 宮部氏が“攻め”、記者は“答えを持たず受け”に回りがち。
- 「昨日と言っていることが違う」「一次確認がない」等の指摘が繰り返され、配信の中では記者側が劣勢に映る編集/展開。
- タイトルどおり、**「石橋記者の負け」**という物語線を強く訴求。
川崎市長選(10/26)との関係
- この応酬は、宮部陣営の主要争点(情報公開・人権/同和事業の検証・メディア批判)を有権者に可視化する狙い。
- “制度とメディアの癒着”イメージを喚起し、改革・追及型の候補像を強調。
- 投票直前に“報道の信頼性”を争点化し、反発票・無党派の注意を引く効果を狙っている。
まとめ
- 配信は「一次資料に当たらない報道は誤報を生む」「非開示は不正の温床」という宮部氏の主張を、石橋記者とのやり取りを通じて観客に体感させる構成。
- 具体資料のその場提示が乏しい記者側は、説得力で劣後。番組内の勝敗は宮部氏優勢の印象で終わる。
最後に。宮部龍彦さんのYouTubeチャンネルのトップに貼ってある動画です。
要約は以下の通り。
音声文字起こしのノイズが多いですが、内容から把握できる範囲で“詳しめに”要約しました。
要約(ひと言)
2014年、津市役所の教育長室で、来庁者が「同和」を持ち出しつつ差別語や威圧的発言で職務対応を強要しようとする“エセ同和”型クレーム事案。職員は記録化・注意喚起を行い、面談の打ち切り方向へ収束させる。
何が起きたか(時系列)
- 来庁者が教育分野の苦情を口実に面談を要求。
- 発言は終始攻撃的で、差別語や外国人蔑視表現、人格否定を多用。
- 「同和」「教育基本法」「日本国憲法」等を断片的に引用し、“自分は正当だ”と強弁。
- 「責任問題になる」「巡査部長」など、権威・処罰をほのめかす言辞で威圧。
- 職員側は「聴取します」「記録します」と告げ、庁内手続に沿った対応を継続。
- 来庁者の発言がエスカレートし、職員が“行き過ぎた発言”を指摘して抑制・打ち切りのトーンへ。
- 最終局面で職員が「その言葉は二度と言うな」と強く制止し、面談は事実上の終結。
来庁者の手口(典型的“エセ同和”パターン)
- ①同和を盾にとった身分/権利の主張(具体的根拠は示さない)
- ②差別語・外国人蔑視・罵倒の連発で心理的優位を取ろうとする
- ③法令名(憲法・教育基本法)を乱発して“法的正当性”を装う
- ④「責任問題」「警察」など強制力を示唆して脅しをかける
- ⑤話題を横滑り・拡散させ、論点を曖昧化して譲歩を引き出そうとする
職員側の対応ポイント(本件で見られたもの)
- 記録化の明示:「聞き取りをします」「記録します」と手続を前面に。
- ルールへの回収:庁内の決裁・所管手順に沿って処理することを繰り返し告知。
- 不当発言の可視化:差別的・威圧的な言葉を“行き過ぎ”として明確に指摘。
- 打ち切りの判断:安全・秩序確保の観点から面談継続の限界を示し終了方向へ。
何が問題行為か(法務・総務の観点)
- 脅しに類する威圧的言動(職務上の不当な圧力)
- 差別的・侮辱的言辞による人権侵害のおそれ
- 根拠なき“同和”主張を用いた便宜供与の要求(不当要求)
- 長時間化・論点拡散による公務妨害リスク
自治体・企業が学べる実務対応メモ
- 事前:面談は原則アポイント制・複数名対応・録音/記録(法令・要綱の範囲で)
- 受付:目的・要望・根拠(案件番号・法令条文等)を初手で確認し、書面化
- 進行:所管・手続・標準処理期間を明示し、脱線を都度戻す
- 禁止ライン:差別語・威圧・脅迫が出た時点で注意→是正されなければ打ち切り
- 安全:庁舎管理権に基づく退去要請、必要に応じ警察通報の基準をマニュアル化
- 事後:記録の保存、庁内共有、再来庁時の対応フラグ、職員メンタルケア
本件の意義
- “同和”を免罪符にした不当要求の典型事例。
- 記録化・複数対応・ルール回帰・打ち切り判断という基本動作が有効であることを示す。
- 自治体・企業の研修教材として、人権配慮と不当要求排除の両立手順を考える素材。
(付録)現場で使える定型フレーズ例
- 「本件は所管手続に従って記録し、決裁ルートで対応します。」
- 「差別的/威圧的なご発言は対応できません。是正いただけない場合は面談を終了します。」
- 「具体的な根拠資料(文書・条文)をご提示ください。確認後、書面で回答します。」
- 「庁舎の安全管理上、これ以上の面談継続はできません。本日はここで終了します。」
こういった組織と闘ってきたのが宮部龍彦候補です。
今回の川崎市長選挙2025、是非とも宮部龍彦にご投票ください。


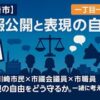









コメント
お疲れ様でした。
敗因は市を任せてもよい安心感が無いことだと思います。
立花孝志さんがお金をくれと配信後、私は振り込みました。
喋ったこともないし、会ったこともないですが連日顔を見てると一万円くらいあげようかなーという気になります。
実際のところお金をあげる義理なんて全く無いのですが。
だから駅立ちやボランティア活動など面着の活動って大事です。
第四の壁を突破することです。