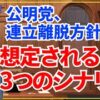10月4日に高市早苗さんが自民党総裁になりました。
その後、紆余曲折がありましたが、高市早苗さんが総理大臣になりました。
期待の大きな高市政権ですが、さっそく増税の話が…。
自民、租特改廃・金融所得課税強化を提起 ガソリン減税の恒久財源案https://t.co/urRKbyWg9y
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) October 22, 2025
自民、租特改廃・金融所得課税強化を提起。ガソリン減税の恒久財源案:ガソリン税暫定税率廃止の財源に、自動車関係課税の強化を言い出すのが自民党クオリティ。国民が求めたのは減税=国民負担の軽減で、それに応えなかったから自公が選挙で大敗したことに小野寺税調会長はまだ気がついていないようだ… pic.twitter.com/Ffqvhj47zy
— 金子洋一神奈川20区(相模原市南区、座間市)元参議院議員 (@Y_Kaneko) October 23, 2025
自民、租特改廃・金融所得課税強化を提起。ガソリン減税の恒久財源案:ガソリン税暫定税率廃止の財源に、自動車関係課税の強化を言い出すのが自民党クオリティ。国民が求めたのは減税=国民負担の軽減で、それに応えなかったから自公が選挙で大敗したことに小野寺税調会長はまだ気がついていないようだ。これではあいかわらずペイアズユーゴー原則から抜け出ておらず、税の置き換えに過ぎない。高市政権にとって試金石であり、この点についてできるだけ早く認識を改めてほしい。
また、恐ろしいのは立憲民主党側がこの提案に乗っかってしまいかねないことだが、その点は大丈夫なのか。
ここで陥りがちな考え方としてペイアズユーゴーがあります。
ペイアズユーゴー(Pay-as-you-go、略:PAYGO)とは、「新たな減税や歳出拡大を行うときは、同時に同額の財源(増税や別の歳出削減)を用意して、収支の悪化を出さないようにする財政ルール」のことです。
ざっくり一文
減らす(税収)か増やす(支出)なら、その場でどこかを増やす(税収)か減らす(支出)で相殺しなさい、という決まり。
仕組み(超シンプル式)
- 変更後の歳入−歳出 ≧ 変更前の歳入−歳出
- 例:ガソリン税1.5兆円減 → 同時に1.5兆円の増税 or 歳出削減をセット
使われ方
- 米国連邦議会で発達(立法のたびに赤字を増やさない規律)
- 日本でも「税制改正大綱」等の議論で慣用的に用いられる考え方(法定の包括ルールというより“運用上の原則”として登場)
長所
- 赤字の垂れ流しを防ぐ
- 施策ごとの費用対効果を厳しく点検しやすい
短所(今回の論点に関係)
- 年度末に税だけで調整すると「減税=他税の増税」が自動化しやすい
- 景気対策の機動性が落ちる(不況時の財政拡大を抑えがち)
- 成長による自然増収や、中期の歳出改革を評価しにくい
代替・補完アイデア
- 中期枠(数年のプライマリーバランス目標)での整合
- 年前半に「減税額・歳出枠・税収見通し」を国会で先に決め、年末は微修正だけにする運用変更
- 一時的措置は補正で賄い、中期で歳出改革・成長増収で整える
一言で言うと、「今やる政策のツケを未来に回さないための同時相殺ルール」。ただし適用タイミングや設計を誤ると、“減税したら別の増税で帳尻”の悪循環になりやすい、というのが今回のポイントです。
チャンネルくららの解説動画を紹介します。
要約は以下の通り。
動画の要旨を、結論→論点→原因(プロセス)→処方箋→タイムラインの順で詳しめにまとめました。
結論(動画の主張)
- ガソリン税の暫定税率と「軽油引取税の上乗せ」は今年からやめられる。財源は“給付金2万円(約2兆円)を中止した分”で十分に充当可能(必要額は約1.5兆円)。
- 自民党税調(与党税制調査会)が示す「他税で穴埋め(金融所得課税・自動車関連増税・租税特別措置いじり)」は本末転倒。
- 問題の根源は“スケジュール設計”。税調を年末に回す現行手順だと「減らすなら別の税を上げる」以外の選択肢がなくなる。
- 解決策は、減税・歳出・税収見通しのフレームを「年の前半(国会)」で先に決め、骨太方針・概算要求に反映させること。
主要論点(何が“ナンセンス”なのか)
- ガソリン税を下げて自動車関連を増税?
政策目的と手段が逆立ち。利用者負担をただ付け替えているだけで景気下支え効果も薄い。- 金融所得課税の引き上げで穴埋め?
成長投資の芽を削ぐ議論。租特は“全面整理+法人税率を下げる”のが公平で筋が良い。- 「必ずペイアズユーゴー」思考の固定化
“何か下げたら同額上げる”前提が強すぎる。初年度は補正の組み替えで賄え、翌年度以降は“成長増収+歳出見直し”で吸収可能。なぜ歪む?(プロセスの構造問題)
- 6月:内閣が骨太方針
- 7月:財務省が概算要求基準(各省に“使い道”の枠配布)
- 8月末:各省が要求提出/税収見通しも並行で固まり始める
- 9–10月:歳出(「使う方」)は実質ほぼ固まる
- 11–12月:最後に与党税調で税制だけ議論 → 既に歳出が固いので、減税=どこかを“増税”で埋める構図になる
→ 結果、「税だけのセクショナリズム」化。組織内で“配る班(補正)”と“取る班(税調)”が別建てで相互参照が機能不全。具体的な処方箋(制度運用の入れ替え)
- 今年度(初年度)
- 岸田政権が計画していた全国民2万円給付(約2兆円)中止分を、**ガソリン暫定税率・軽油引取税上乗せの廃止(約1.5兆円)**に充当。追加増税は不要。
- 来年度以降
- 4月までに「税収増見込み+歳出削減パッケージ」を内閣として用意。
- 4–5月に自民・維新等で合意形成し、6月の骨太へ格納。
- 7–8月の概算要求・予算編成を“減税前提”で動かす。
→ こうすれば年末税調は“微修正の場”になり、「減らすなら必ず上げる」の呪縛から抜けられる。評価・示唆
- 税調の人事(例:外部から小寺氏を起用)だけでは限界。順序の再設計が要。
- 首相が力技で例外処理(岸田政権の一時的な個人減税のように)も可能だが、毎年は非現実的。恒常運用に落とすべき。
- 成長と減税をセットにするため、租特は包括整理+法人税率引下げの方向が一貫して合理的。
実務タイムライン(提案モデル)
- 〜4月:税収見通し(成長前提)+歳出削減案を内閣で確定
- 4–5月:与党・連立与党で合意(参院情勢も勘案)
- 6月:骨太に反映(「減税額・歳出枠・税収前提」を明記)
- 7–8月:概算要求・査定を“減税内蔵”で進行
- 9–10月:歳出ほぼ確定
- 11–12月:税調は微調整のみ(“穴埋め増税”に頼らない)
まとめ(一言)
- 増税で穴埋めする前に、給付中止分の2兆円→燃料減税1.5兆円に即充当。
- 年末税調まかせをやめ、年前半の国会で“使う・減らす・入る”の大枠を先に決める。 これが「高市政権VS自民党税調」の本当の勝ち筋、というのが動画の骨子です。
減税のための財源を他の増税で穴埋めという発想、ペイアズユーゴーからの脱却が必要と思います。
緊縮財務省の縛りから脱却を#おはよう寺ちゃん
民主党政権下、平成22年6月22日 閣議決定
“財源確保ルール(「ペイアズユーゴー原則」)
歳出増・歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、恒久的な歳出削減・歳入確保措置により安定的な財源を確保”https://t.co/TgV10hJ9n0 pic.twitter.com/veBoJVjFNR— 質問者2 (@shinchanchi) December 12, 2022